麻雀を始めたばかりの初心者にとって、「どうやって牌を組み、どのタイミングでアガるのか」は最初の大きな壁です。
本記事では、麻雀の基本となる4メンツ1雀頭の構成や、リャンメン・カンチャン・ペンチャンといった待ちの形、そしてリーチ・タンヤオ・ピンフなど初心者が優先して覚えたい役をわかりやすく解説します。
さらに、ツモ・ロンの点数計算の超基礎や、上がり方一覧である役の早見表、フリテンや多面張見落とし等の初心者が陥りやすいミスの防止策までカバーしています。
役や点数を効率よく暗記できるPDF・アプリ・フラッシュカードの紹介も行っており、学習と実践をスムーズにつなげられる構成になっています。
初心者が実戦で困らないための知識と、アガリの精度を高める手順が満載なので、ぜひ本記事を繰り返し活用して、安定して勝てる麻雀力を身につけていきましょう!
麻雀の上がり方の基本形の組み合わせと役一覧を完全解説
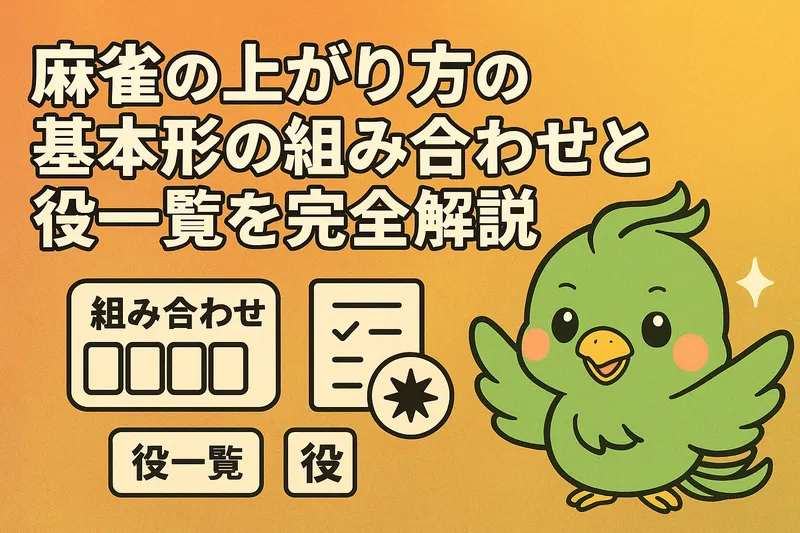
基本形の”4メンツ1雀頭”と例外形の”七対子&国士無双”
麻雀は順子or刻子×4 + 雀頭×1=14枚でアガリ形が完成します。この構造は「4メンツ1雀頭」と呼ばれ、すべての基本となる形です。
メンツは順子(

 など連番3枚)または刻子(
など連番3枚)または刻子(

 など同牌3枚)で構成され、これを4組揃え、さらに雀頭と呼ばれる対子(
など同牌3枚)で構成され、これを4組揃え、さらに雀頭と呼ばれる対子(
 など同じ牌2枚)を1組加えることでテンパイ状態となり、アガリが可能になります。
など同じ牌2枚)を1組加えることでテンパイ状態となり、アガリが可能になります。
順子や刻子の組み合わせは非常に多彩で、牌効率や手役を考慮しながら構築していくのが麻雀の醍醐味でもあります。テンパイ=アガリ一歩手前の状態に到達すると、自分がアガリ牌を引く(ツモ)か他家の捨て牌でアガる(ロン)ことができます。
ただし、例外的なアガリ形も存在します。たとえば七対子(チートイツ)は対子を7組揃える特殊なアガリ形で、メンツを一切含まないため通常構成とは異なる例外形です。形は特殊ですが、構築しやすく、初心者でも狙いやすい役として人気があります。
同じく国士無双(こくしむそう)はもっと異端で、么九牌(1・9の数牌+字牌)13種すべてを1枚ずつ揃えた上で、そのうち1種類を対子とする構成です。これは役満と呼ばれる最高点の役に該当し、アガれば一発逆転も夢ではありません。
初心者はまず「メンツを4つ作るリズム」を体に叩き込むことが大切です。七対子は対子が増えたら狙う、国士無双は么九牌が9種以上になったらスイッチする、といった判断基準を持っておくと混乱せずに済みます。
麻雀のルールを漫画で分かりやすく書かれているので、詳しく知りたい方は購入をおすすめします!Amazonで購入すると、安く手に入るためおすすめです!
順子・刻子・槓子・雀頭とは?基本用語の具体解説
◆ 順子とは?
順子(しゅんつ)は同じ種類の数牌で連続した3枚の組み合わせを指します。たとえば

 や
や

 など、萬子・筒子・索子のいずれの色でも構成できます。ただし、字牌(東南西北白發中)は数の概念がないため順子にはなりません。
など、萬子・筒子・索子のいずれの色でも構成できます。ただし、字牌(東南西北白發中)は数の概念がないため順子にはなりません。
順子は牌効率に優れており、他の形に変化しやすいため手作りの中心となるパーツです。端牌より中張牌で構成された順子のほうが受け入れが広く、初心者でも作りやすい傾向にあります。
◆ 刻子とは?
刻子(こーつ)は同じ牌を3枚揃えるセットです。例として

 や
や

 のように、まったく同じ牌3枚を揃えることで成立します。萬子・筒子・索子はもちろん、字牌でも刻子は作ることができます。
のように、まったく同じ牌3枚を揃えることで成立します。萬子・筒子・索子はもちろん、字牌でも刻子は作ることができます。
特に役牌(白・發・中や自風・場風)の刻子は、鳴いても1翻がつく貴重な得点源になります。ドラが刻子になった場合は一気に打点が跳ね上がるため、積極的に狙う価値がある形です。
◆ 槓子とは?
槓子(カンツ)は同じ牌を4枚揃えるセットで、刻子より1枚多い構成です。たとえば


 や
や


 のように完全に同一の牌を4枚揃えることで成立します。
のように完全に同一の牌を4枚揃えることで成立します。
槓子を作ることで加カン・暗カン・大明カンといったアクションが発生し、それぞれに応じてドラ表示牌が増えたり、特殊なルールが適用されたりします。
特に暗カンは自分だけで完結するため守備力を落とさずに高得点を狙える魅力がありますが、ドラが増え、他家の打点が高くなるリスクがあるため、状況を見極めて判断する必要があります。また、槓子を含む手は符計算上も点数が高くなりやすいため、うまく活用できれば大きな得点源になります。
◆ 雀頭とは?
雀頭(じゃんとう)は対子=同じ牌を2枚揃えるセットで、アガリに必ず必要な1組のパーツです。たとえば
 や
や
 のように2枚1組であれば成立します。
のように2枚1組であれば成立します。
雀頭は単体では点数になりませんが、役牌が雀頭になった場合はピンフが付かなくなるなど、他の役と関連して役の成立に影響を与えることがあります。初心者は役牌の対子を雀頭にするか、他の順子・刻子とのバランスで使い分けることが重要です。
全役・翻数・成立条件を網羅した早見表
役は1翻~役満まで37種(一般ルール)あり、早見表で丸暗記が最短ルートです。
| 翻 | 代表役 | 鳴き可否 | 得点例(子・ロン) |
|---|---|---|---|
| 1翻 | リーチ/タンヤオ/ピンフ | リーチ×鳴き不可/タンヤオ○/ピンフ× | 30符1翻=1,000点 |
| 2翻 | 三色同順/イーペイコー | 三色○/イーペイコー× | 30符2翻=2,000点 |
| 3翻 | 純全帯么/混一色 | 鳴くと1翻減 | 30符3翻=3,900点 |
| 役満 | 国士無双/四暗刻ほか | ― | 役満=32,000点 |
図解付きの役一覧をまとめていますので、全役の詳細を具体的に覚えたい方はぜひ見てください!
「頻出役→高打点役→役満」と段階別に覚えると頭がゴチャつきません。
ロンとツモの所作+点数計算の超基礎
ロンは他家の捨て牌でアガり「放銃者のみが支払う」仕組み。発声→手牌公開→点数申告が鉄則で、形式を誤るとチョンボになることもあるため要注意です。
ツモは自分で引いた牌でアガる形で、子なら他3人から1,000点ずつ、親なら2,000点ずつと、支払う相手全員が対象になります。アガリ方によって点のもらい方が大きく変わる点は覚えておきたいポイントですね。
※ロンとツモの漢字を知ると、それぞれの違いを覚えやすいので、「麻雀におけるロンとツモの漢字」を開設した記事も是非併せて、ご覧ください。
そして、点数は符×翻で決定され、符は最低20符、10の倍数で切り上げるのが基本ルールです。翻数が同じでも符が多ければ点数が大きくなり、40符2翻=2,000点、50符2翻=2,400点…と変化します。計算に慣れないうちは点数早見表を手元に置いて確認するのが安心です。
初心者はまず「副底20符+面子符+待ち符」という構造を押さえましょう。特にリャンメン待ちと単騎待ちでは符が異なるので、実戦での経験が計算力を鍛えてくれます。
点数計算の早見表や、効率的な勉強方法、AIカメラアプリ等を幅広く紹介した記事をまとめていますので、是非読んでみてください!
麻雀の上がり方と組み合わせのコツを初心者向けの解説

順子・刻子・槓子・雀頭の作り方とコツ
さらに、牌の組み合わせにおいて意識しておきたいのが「変化の可能性」です。
たとえば順子を構成する際、

 のような中張牌の順子であれば、周辺牌(3や7など)からの変化で新しいメンツが生まれやすくなります。一方で、
のような中張牌の順子であれば、周辺牌(3や7など)からの変化で新しいメンツが生まれやすくなります。一方で、

 や
や

 のような端に寄った順子は変化が限られるため、状況に応じて見切る判断も重要です。
のような端に寄った順子は変化が限られるため、状況に応じて見切る判断も重要です。
刻子・槓子については、「守備と打点のバランス」も考えたいポイントです。例えばドラや役牌の刻子は守備的な活用にもなり、終盤に強い形として残しておく選択肢もあります。槓を選ぶタイミングでは、他家のリーチ気配や場の巡目を意識して慎重に行いましょう。
雀頭は単なる対子ではなく、「最終的な形への影響力を持つパーツ」です。リャンメン待ちになるか、単騎待ちになるかで点数やアガリやすさが大きく変わるため、テンパイを見据えた時点での雀頭候補の見直しが有効です。特にピンフ狙いでは数牌の対子が優先されることも覚えておくとよいでしょう。
このように、順子・刻子・槓子・雀頭を「作る」だけでなく「使い分ける」視点を持つことで、打牌の質がワンランクアップします!
リャンメン・カンチャン・ペンチャン受け入れ比較
リャンメン(両面)
- 形の具体例:


- 受け入れ枚数:8枚(2種×4)
- 変化の伸びしろ: すでに良形のため変化の必要は少ないが、


 など中張牌の両面なら引き入れ次第で多面張へ拡張する余地もある。端寄り(、
など中張牌の両面なら引き入れ次第で多面張へ拡張する余地もある。端寄り(、
 ・
・
 )は受け入れこそ同じでも手役が限定されやすい。
)は受け入れこそ同じでも手役が限定されやすい。 - 参考情報:麻雀の両面(リャンメン)待ちを完全解説!和了率と押し引きの最適解
カンチャン(嵌張)
- 形の具体例:


- 受け入れ枚数:4枚(1種×4)
- 変化の伸びしろ: 隣接牌を 1 枚引くだけでリャンメンに昇格しやすく、打点・速度ともに大幅アップが見込める。序盤はリャンメン化を狙い、中盤以降は速度を優先して処理するのがセオリー。
- 参考情報:麻雀のカンチャン待ちの強さ・変化と戦術を分かりやすく解説
ペンチャン(辺張)
- 形の具体例:


- 受け入れ枚数:4枚(1種×4)
- 変化の伸びしろ: リャンメン化には 2 段階(カンチャン→リャンメン)のツモが必要で実質的な伸びしろは極小。端牌ドラ受けなど局所的な価値を除き、優先度は低い。
- 参考記事:麻雀のペンチャン待ちとは?両面・カンチャン比較と有効活用を徹底活用!
具体例で理解する待ち形の優先度
- リャンメン重視で速度確保
例:
 の2枚で受け入れ枚数が8枚であり、牌効率は非常に高い良形のため、基本戦術としてはリャンメンの形を目指すのが良い
の2枚で受け入れ枚数が8枚であり、牌効率は非常に高い良形のため、基本戦術としてはリャンメンの形を目指すのが良い - カンチャンは変化読みがカギ
例:手牌が
 →
→  ツモで
ツモで 
 の両面に変化、序盤保持は◎。
の両面に変化、序盤保持は◎。 - ペンチャンは早めの整理が基本
例:
 →
→  受けのみ。ドラ絡みが無ければ安全牌に転用する方が平均収支アップ。
受けのみ。ドラ絡みが無ければ安全牌に転用する方が平均収支アップ。
リャンメン・カンチャン・ペンチャンのまとめ:
受け入れ枚数で見ると リャンメン > カンチャン > ペンチャン。変化の期待値も同順序で下がるため、手作りではリャンメン優先、カンチャンは変化前提、ペンチャンは特殊事情がない限り早期処理が合理的です。
PDF・アプリ・暗記カードで役と点数を効率習得
1. PDF早見表&印刷ツール
- 麻雀役一覧+点数表(OneMoreMJ):A4サイズで役条件と点数早見を両面レイアウト。卓横に貼ると即確認できる定番資料。(mj-onemore.com)
- 点数早見表ポスター(雀記):親子の点差が一目でわかる大型ポスター。AI/PDFデータ両対応で自宅プリンターでも印刷可。(janki.jp)
活用TIP:
A4に縮小印刷→ラミネートして“卓上カード”化すると、オンライン対局中でもすぐに確認できます
2. 点数計算&学習アプリ
- 書いて覚えて強くなる! 麻雀点数計算 魔法のドリル:点数計算のための麻雀書籍!点数計算早見表を見なくても、点数計算を覚えれる構成が特徴です!
- 麻雀点数計算マスター:授業形式でクイズを解きながら楽しく基礎学習できる。
3. ゲーミフィケーション学習
- 麻雀入門(コモレビ):役作りをステップ式ミッションで習得。初心者でも飽きずに学べると高評価。
4. フラッシュカード
- Quizlet「麻雀役」デッキ:スマホでスワイプ暗記。ランダムテストで“役名→翻数”の即答力が鍛えられる。
初心者向けに麻雀の上がり方のための役一覧と陥りやすいミス一覧を紹介

覚えるべき主要役と優先順位
役を覚える際のコツは「出現頻度 × 打点期待 × 鳴きの可否」で優先度を決めることです。ここでは初心者がまず体に染み込ませたい“実用役”をTier方式で整理しました。
■ Tier 1|最優先で体得
- リーチ(面前限定/鳴き不可)
- 面前なら必須。裏ドラ・一発で爆発力◎。攻守のスイッチ役。
- タンヤオ(面前可/鳴き可)
- 鳴いても1翻。2‑8牌だけで手組が簡単、速度トップ。
- ピンフ(面前限定/鳴き不可)
- 両面待ち固定で20符。門前主体なら頻出No.1。
- 役牌(白發中/自風・場風)(鳴き可)
- 刻子で1翻。守備牌にもなる万能力パーツ。
Tips:
- この4役+ドラ表示を“マストチェック”にすると、ほぼ毎局どれかが絡むため序盤の手組が迷いません。
- 配牌時に「両面1組+役牌1組」を探すだけで、手の方向性が瞬時に定まりブレにくくなります。
- 打点不足を感じたら赤ドラや表ドラに絡む牌を1ブロックだけ残す意識を持つと、平均打点が向上します。
■ Tier 2|高打点を狙うステップアップ役
- 七対子(チートイツ)(面前限定)
- 対子×7で1翻。変化は少ないが安全牌を抱えやすく守備力◎。
- 混一色(ホンイツ)(鳴き可)
- 一色+字牌。鳴いても2翻、門前で3翻と安定打点。
- 清一色(チンイツ)(鳴き可)
- 同色のみで門前6翻・鳴き5翻。爆発力最強クラス。
- 国士無双(面前限定)
- 么九牌13種+対子1組で役満。配牌から狙える逆転候補。
Tips:
- 七対子は受け入れが重なりやすい配牌で狙うと効率的。
- ホンイツ・清一色はドラ色と場に捨てられた牌の偏りを見て決断。
- 国士無双は9種以上の么九牌があればスイッチを検討しよう。
■ Tier 3|状況次第で狙う中級役
- 三色同順(鳴き可)
- 数牌3色の同一順子。タンヤオと高相性、鳴きでスピードも◎。
- 一気通貫(イッツー)(鳴き可)
- 同色123‑456‑789。染め手意識で狙うと打点上昇。
- チャンタ(混全帯么)・純チャン(純全帯么)(鳴き可)
- 初心者は鳴きチャンタで手役感覚を養うのに最適。
Tips:
- 三色同順は配牌で類似順子が複数色に散らばっている時に意識すると成功率アップ。
- チャンタ系は字牌の活用がカギ。鳴きやすい字牌を軸に手をまとめ、速度と打点を両立させよう。
- Tier3役は狙いすぎると速度負けしやすい。テンパイまで3手以上かかる場合は速度重視に切り替えるのが吉。
麻雀初心者が陥りやすいミス
麻雀初心者がオンライン/卓上共通でよく初心者が誤りやすいミスの例を3つ紹介します。
1. 鳴きで 役なしテンパイして、上がれない
- 実例:鳴いて聴牌したものの役がなく、上がれない
- 防止策:鳴く前に最低でも1つの役があるかを確認。
- 参考記事:麻雀の鳴きがOKな役・NGな役を完全解説!麻雀の鳴き判断ガイド【初心者OK】
2. 待ち牌の見落とし(多面張スルー)
- 実例:多面張の無意識にを見逃しチョンボ
- 防止策:テンパイ後に 受け入れの牌を確認。複雑な形はスマホアプリの何切る問題で事前トレーニング 。
- 参考記事:麻雀の待ち牌当てスキルをアプリで楽しく上達!初心者から実戦力アップまで完全ガイド
3. フリテンリーチ
- 実例:捨て牌にアガリ牌が含まれたままリーチ→アガれず失点
- 防止策:リーチする前に上がる前に自分の河に上がり牌がないか確認
- 参考記事:
(総括)麻雀の上がり方一覧と牌の組み合わせの初心者向けまとめ
▼この記事のポイントまとめ

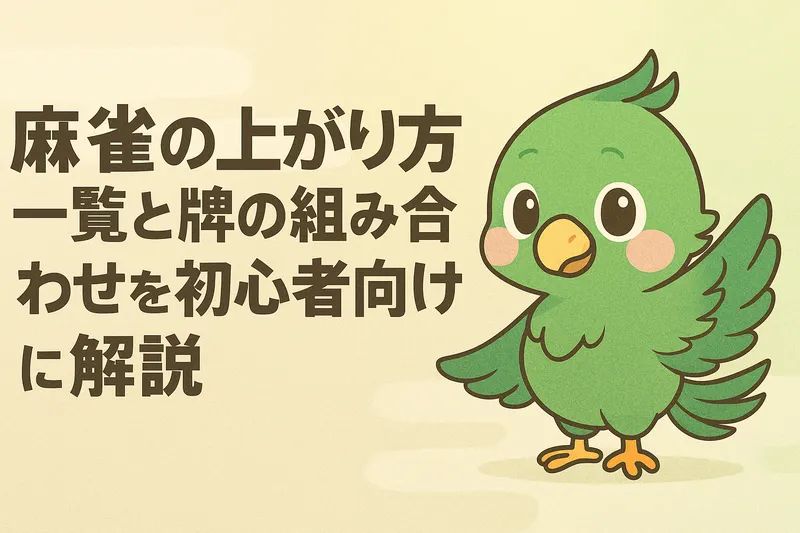




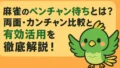
コメント