麻雀における「門前(メンゼン)」と「門前清(メンゼンチン)」は、どちらも“鳴かない状態”を示しますが、国によって、それぞれに異なる定義と使われ方があります。本記事では、門前の状態や門前清自摸和(メンゼンツモ)をはじめとした門前役の種類と特徴、副露がもたらす影響、そして門前を活かす戦術について解説します。
リーチ・平和・一盃口・七対子・二盃口といった門前限定役の基本や、副露と門前状態の関係、例外として認められる暗槓の扱いなど、門前戦術に必要な知識を網羅的に紹介。また、門前を選ぶべきか鳴きを入れるべきかといった実戦的な判断基準についても触れており、初心者が抱きやすい疑問や迷いにも答える内容となっています。
この記事を読むことで、門前と門前清の違いだけでなく、局面に応じた戦術選択まで自信を持って判断できるようになるはずです!
麻雀の門前(メンゼン)・門前清(メンゼンチン)とは何か?

門前(メンゼン)の定義と「閉じ手」の考え方
門前とは、他家の捨て牌を一切ポン・チー・明槓しないまま、終始自分のツモだけで手牌を構成していく“閉じ手”の状態を指します。スタート時点の14枚(親)/13枚(子)から始まり、ツモのみで手牌が変化するため、他家に手の内を読まれにくく、打ち筋を見せずに構想を練ることができるのが特徴です。
門前を維持していると、リーチや平和、一盃口、門前清自摸和(メンゼンツモ)といった「門前役」の成立条件をクリアし、複合によって高打点の和了を狙えるチャンスが広がります。特にリーチをかけた状態からの和了では裏ドラや一発の恩恵も得やすく、門前ならではの爆発力が魅力です。
さらに、門前ロン(鳴かずにロン和了した場合)では10符が加算されるため、符計算の面でも得点が伸びやすいというメリットがあります。ただし、ポン・チー・明槓・加槓といった副露を宣言した瞬間に門前状態は崩れ、それ以降は門前役が付かなくなる点には注意が必要です。
門前清(メンゼンチン)の意味と使われ方
門前清(メンゼンチン)は、門前状態を保ったままツモ和了したときに成立する1翻役「門前清自摸和(メンゼンツモ)」の略称として広く使われています。つまり、「門前清」という言葉は、厳密には門前状態のまま自摸で和了した結果として得られる役名を指す用語です。
ただし、中国語圏など一部では「門前清」が門前状態そのものを意味する場合もあり、言語や文化によって解釈が異なることがあります。一方、日本の公式役表においては「門前清」は単独で役として扱われることはなく、あくまでも「門前清自摸和」の略語や強調表現という扱いに留まります。
混乱を避けるためにも、麻雀においては「門前」は鳴かない状態を指す用語、「門前清自摸和(メンゼンツモ)」はその状態を保ったままツモ和了を達成したときに得られる正式な役名、というふうに分けて理解することが重要です。
副露しない進行と門前が崩れるタイミング
門前が崩れるのは、ポン・チー・明槓・加槓(加カン)を宣言した瞬間です。これらはすべて副露行為に該当し、自分の手牌を公開して他家の牌を利用する形になるため、「閉じ手」の状態が崩れてしまいます。
このタイミングで門前役(リーチや門前清自摸和など)が無効となり、それ以降は門前としての特典を得られなくなります。
逆に、暗槓(暗カン)は例外で、すべて自分の手牌だけで行う行為なので門前状態を維持したまま進行可能です。この点は初心者が混同しやすく、注意が必要です!
また、錯覚しがちな点として「副露を取り消す」ことはできません。たとえば、うっかりポンしてしまった場合や、誤操作による鳴きもすべて正式な副露として扱われます。
さらに、「門前状態に戻す」ルールは存在しないため、一度でも副露をしたら門前としての資格は失われます。オンライン麻雀や自動卓ではこの処理が自動的にされるため問題は少ないですが、リアル麻雀では宣言の取り扱いに細心の注意を払いましょう。
麻雀の門前清自摸和(門前清)とは?門前役の基礎
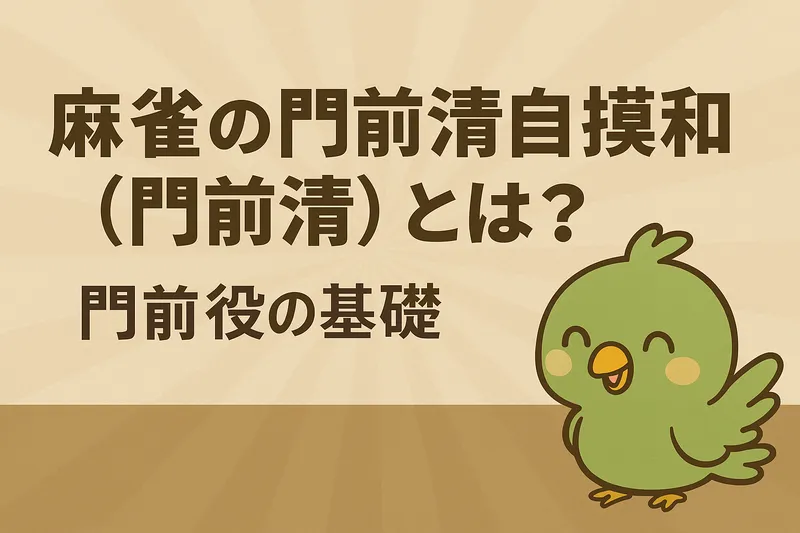
門前清自摸和(メンゼンツモ)の成立条件
門前清自摸和は「門前+自摸」の組み合わせで成立する、非常に基本的かつ重要な1翻役です。門前状態を維持しつつ自摸でアガることによって成立するこの役は、初心者から上級者まで広く利用されており、門前戦術の基本中の基本といえるでしょう。
具体的な点数計算の一例を挙げると、40符2翻の場合、子であれば7,700点、親であれば11,600点となります。この点数は門前加符10符が乗らないツモ計算特有の形であり、ロン和了時とは計算方法が異なるため注意が必要です。点数計算の覚え方をまとめた記事がありますので、ぜひ読んでみてください!
また、門前清自摸和は符計算にも大きく関わる役です。副底の20符に加えて、待ち形(単騎待ち・嵌張待ちなど)による加符、さらに暗刻や雀頭の種類(役牌かどうか)などによって符が加算されるため、基本的な符計算ルールに慣れておくことが重要です。
この役は単体で1翻ですが、リーチや平和(ピンフ)などの他役と組み合わさりやすく一気に高打点化する可能性を秘めています。門前清自摸和を正確に理解し、スムーズに計算できるようになると、麻雀の得点計算全体が一気にクリアになるはずですよ!
門前限定の役と門前清自摸和のコンボ戦術
リーチや平和など、門前でしか成立しない役は打点・圧力ともに非常に優秀で、門前清自摸和はこれらを複合しやすく、門前で複数の役が絡むと一気に跳満・倍満級の和了を狙うことも可能です。
以下は、門前状態を維持することで成立する門前限定役(役満除く)の一覧です:
| 役名 | 翻数 | 条件概要 |
|---|---|---|
| リーチ | 1翻(門前限定) | 門前で聴牌した状態で立直宣言。裏ドラ・一発・他役複合で打点上昇が見込める。 |
| 門前清自摸和 | 1翻(門前限定) | 門前状態で自摸和了した場合に成立。 |
| 平和(ピンフ) | 1翻(門前限定) | すべて順子構成・役牌以外の雀頭・両面待ち。 |
| 一盃口(イーペーコー) | 1翻(門前限定) | 同一の順子を2組作る。門前状態でのみ成立。 |
| 二盃口(リャンペーコー) | 3翻(門前限定) | 一盃口を2回作る(同一の順子×2組をさらにもう1セット)。 |
| 七対子(チートイツ) | 2翻(門前限定) | 7つの対子で構成された特殊な和了形。 |
鳴いて上がれる役もあれば、鳴くと上がれない役もあり、大事な麻雀の要素なので、把握することをおすすめします!
麻雀の門前・門前清自摸和(門前清)を活かす実戦活用術とは

門前のメリット・デメリットと手牌効率
メリット:
デメリット:
門前維持は「手牌効率」と「打点期待値」の両睨みが鍵です。序盤の配牌構成とドラとの兼ね合い、相手の打ち筋なども加味して門前を貫くかどうかを見極めましょう!
鳴き判断の基準と局面別の戦術選択
判断基準としては「場況」「親番の有無」「残り巡目」「対戦相手の仕掛け状況」などを総合的に見極めることが重要です。
これらの要素を複合的に捉えることで、単純な手役や打点だけではなく、流れや相手の動向に合わせた最適な判断ができるようになります。特に中盤以降は、他家の副露頻度やリーチの気配なども含めて押し引きのバランスを調整する必要があり、柔軟かつ戦略的な思考が求められます!
判断基準の例:
下記は、よりリアルな何切る形式の押し引きスキル向上の名著ですので、”押し引きをうまくなりたい”という方購入をおすすめします!Amazonで購入すると、安く手に入るためおすすめです!
(総括)麻雀の門前・門前清・門前清自摸和(ツモ)とは?のまとめ
▼この記事のポイントまとめ

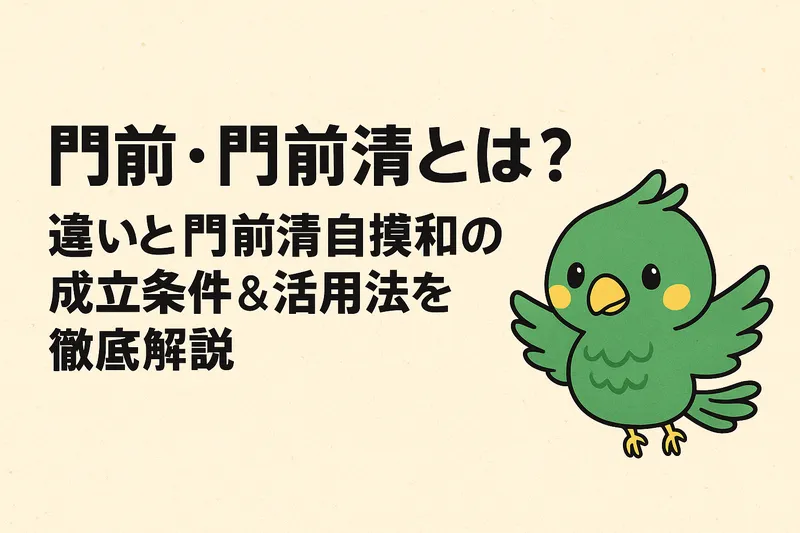
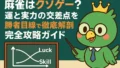
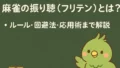
コメント