ウザク本は「何切る」問題に特化した超有名シリーズですが、発売順と難易度順がズレているため、読む順番を間違えて、学習効率がかなり非効率なりやすい本でもあります。
逆に言うと、読む順番を把握して、ウザク本を読むと最速で麻雀強者になれます。
この記事では、最新の金本まで含めた全巻の特徴を整理し、「レベル別にどこから始めるか」「挫折したときの戻り方」まで、ロードマップとしてまとめます。
💡この記事で理解できるポイント
- ウザク本シリーズ(白・緑・金・赤・青)の役割と難易度、想定レベル
- 「発売順」と「難易度順」が違う理由と、学習効率を重視したおすすめの読む順番
- 完全初心者〜上級者までのレベル別「ここから始める」具体的ステップ
- 他の牌効率本・何切る本・アプリとの組み合わせによる、最短上達プラン
ウザク本の順番の結論と全体像

まずは、シリーズ全体のラインナップと「結局どの順番で読むべきか」の結論を先にまとめます。
まず知ってほしいウザク本の読む順番
ウザク本のもっともオーソドックスで失敗しにくい読む順番はこれです。
- 白『はじめの書』
- 初心者向け。基本ルールや配牌からアガリまでの流れを丁寧に学べます。
- 緑『牌効率』
- 初級~中級向け。牌効率の基礎を体系的に理解し、手作りの精度を向上。
- 金『何切る金』
- 中級向け。似たような牌姿を比較しながら判断速度を高め、実戦での迷いを減らします。
- 赤『定石301選』
- 中級~上級向け。より実戦的な何切る問題を通じて、場況判断や押し引きのセンスを磨きます。
- 青『傑作300選』
- 上級者向け。高難度の理論問題に取り組むことで、高度な雀力を完成させます。順番通りにじっくり学べば、天鳳特上卓でも通用する力がつくでしょう!
下記の順番の狙いはシンプルで、少しずつ階段を上がる形になっているからです。

迷ったらまず「白→緑→金→赤→青」の順番だと思ってね。あとから後半に各ウザク本の内容や身に着くスキルもまとめてるから見てみてね!
ウザク本の基本ラインナップ
現在、ウザク本の中核となるのは次の5冊です(通称と役割もあわせて整理します)。
| 通称 | 書籍 | 主なテーマ | 想定レベル |
|---|---|---|---|
| 白本 | ウザク式麻雀学習 はじめの書 | 1局通しの何切る・基礎思考 | 初心者〜初級 |
| 緑本 | ウザク式麻雀学習 牌効率 | 牌効率の教科書 | 初級〜中級 |
| 金本 | ウザク式麻雀学習 何切る 金 | 中級向け何切る・比較判断 | 中級 |
| 赤本 | 麻雀 定石「何切る」301選 | 押し引きを含む定石何切る | 中級〜上級 |
| 青本 | 麻雀 傑作「何切る」300選 | 高度な牌効率・総合力 | 上級 |
ポイントは、白・緑・金が「ウザク式麻雀学習」シリーズ、赤・青が初期の定番何切るシリーズという構造です。
白と緑は「教科書寄り」、金・赤・青は「問題集寄り」と考えると、役割が分かりやすくなります。
ウザク本の発売順と難易度順の違い
発売順は次の通りです。
- 1冊目:青本(2016)
- 2冊目:赤本(2017)
- 3冊目:緑本(2019)
- 4冊目:白本(2021)
- 5冊目:金本(2024)
一方で、学習効率を考えた難易度順は、ほぼ次のようになります。
白本 → 緑本 → 金本 → 赤本 → 青本
なぜ発売順と違うかというと、
という背景があるからです。
そのため、青本から読み始めるのは、筋トレ未経験でいきなり高重量スクワットをやるようなもので、まずおすすめできません。
レベル別の最適なウザク本と読む順番

ここからは、「自分の今の実力から見て、どの巻から入るか」を具体的に決めていきます。
完全初心者向けの入り方
ここでいう「完全初心者」は、下のようなレベルを想定します。
このレベルからいきなりウザク本に突入するのは、正直かなりキツいです。
おすすめは、という流れです。
- ルール入門書やアプリで、基本的なルール・役・点数計算まで一度通す
- ネット麻雀や友人との対局で、数十局〜100局ほど実際に打ってみる
- そのあとで、白本「はじめの書」に入る
白本は「ルール本」ではなく、
『ルール本を一冊読み終えた人が、初めて戦術に触れるための本』と考えるのがちょうどいいです。
白本に入る目安は、下記をクリアしているかどうかです。
※「麻雀ルールの覚え方」の記事を読むと、上記も1週間程度でクリアできるようになるので、ご覧ください。

麻雀を覚えたてだと、麻雀を実戦するのと並行で本を読むことで、かなり効率的に強くなるので、おすすめです。
麻雀を始めたばかりだけど、今すぐに強くなりたい方は是非読んでみてください!
初級者向けウザク本の順番
ここでは、↓のようないわゆる「初級者」を想定します。
このレベルなら、ウザク本の本格スタートラインに立っているので、
- 白本『はじめの書』
「局の流れ」「5ブロックの感覚」「安全牌を持つタイミング」をつかむ - 緑本『牌効率』
「5ブロック理論・2ヘッド理論・1シャンテンピーク理論」を体系的に学ぶ - 金本『何切る 金』
似た形を比べる問題を通して「中級一歩手前レベルの判断力」を鍛える
という順番がもっとも効きます。

どの本も有名で実績のある本です。特に緑本『牌効率』は、麻雀に慣れだした方にとって、正しい牌効率を教えてくれるから、勝率がかなり上がるよ。
もっとアガりたい、もっと勝ちたい方は絶対に読んでみてね!
この段階では、赤本・青本はまだ手を出さなくて大丈夫です。
無理に触ると、解説の半分以上が頭に入らず、「自分は向いてないのかな…」と勘違いしやすいので注意してください。
中級・上級者の読む順番
中級〜上級者、たとえば
このあたりなら、最初から全巻を視野に入れてOKです。
順番は次のどちらかがおすすめです。
中級寄りの人
- 緑本(まだ読んでなければ最優先)
- 金本
- 赤本
- 青本
上級寄りの人(牌効率の基礎がすでにある人)
- 赤本
- 青本
- 金本(比較問題で感覚を整える)
- 緑本・白本で理論の抜け確認(必要に応じて)
中級〜上級者にとって大事なのは、「自分がどこで負けているかに応じて順番を変えること」です。
上記のように、「弱点ファースト」で巻を選ぶと、伸び方が変わります。

金・赤・青は麻雀が十分打てる方向けの本だよ。麻雀仲間と差を開きたい方や、鳳凰卓や魂天を目指す方は絶対に読んだ方が近道になるよ!
各ウザク本シリーズの特徴と読む順番の根拠

この章では、白・緑・金・赤・青のそれぞれについて、「どんな本なのか」「どの順番で読む根拠があるのか」を詳しく見ていきます。
白本とはじめの書の位置づけ
白本『ウザク式麻雀学習 はじめの書』は、「1局通しの何切る」が最大の特徴です。
- 上段:東1局から南4局まで、配牌〜アガリまでを1巡ずつ何切る形式で追う
- 下段:上段とは独立した、テーマ別のプラス1問(孤立牌処理・スリム化など)
ウザク氏自身のnoteでも語られているように、「はじめの書」というタイトルはかなり議論を呼びました。
白本は本当に初心者向けか?
ここから読み取れる現実的な結論は、
白本は「ルールを一通り理解した初心者〜初級者向け」であり、「役もあやしい完全初心者」の1冊目には重い
ということです。
つまり、下記くらいのイメージがちょうど良いです。
- ルールブック0冊 → いきなり白本→ 挫折しやすい
- ルールブック1冊+数十局の対局 → 白本→ 十分ついていける
白本を読む目的
白本で身につけたいのは、主に次のような感覚です。
白本は、よくある「ルール本」よりも、実戦の流れに即した考え方を体験できる本です。
その意味で、ウザク本シリーズの「入口」として、順番の一番前に置く価値があります。脱初心者のための最適な本なので、ぜひ読んでみてください!
緑本・金本の牌効率強化
ウザク本シリーズで牌効率を専門的に扱うのが、緑本と金本です。
この2冊はセットで見ると理解しやすくなります。
緑本『ウザク式麻雀学習 牌効率』
緑本は「教科書」です。
など、ウザク本全体を通じて使われる重要な理論が、ここで体系的に整理されています。
構成は下記のスタイルで、復習しやすいのもこの本の強みです。
- 1テーマ=見開き2ページ
- 右下にそのテーマの「一言要約」
順番として、白→緑の理由は明確で、
- 白で「局の流れの中での5ブロック」をなんとなく体感
- 緑でその理論を言葉と数字で理解し直す
という流れにすると、知識が一気に安定するからです。我流で鍛えた牌効率も良いですが、一度正しい牌効率を学ぶと、一気に聴牌率・和了率がかなり上がるので、聴牌率・和了率に悩んでいる方は読んで実戦すると、この本の凄さを実感できるはずです!
金本『ウザク式麻雀学習 何切る 金』
金本は、緑本の「問題集版」という位置づけです。
金本で身につくのは、
ただ「受け入れ最大」を選ぶだけでなく、打点・最終形の良さ・リーチ後の待ちの強さまで含めて、どこに寄せるか
という考え方です。
そのため、順番としては、
- 緑本で牌効率の理論(受け入れ比較・5ブロック・複合形)を理解
- 金本でその理論を、実戦的な何切る問題で身体に落とし込む
この2段構えが最も効率的だと言えます。
麻雀をやっていると、この手牌の場合「どっちを切るのが良いんだろう」と思うシーンがありますが、それを解決してくれるのが金本です。かなり実践向きの本なので、次のステップアップの本としてぜひ読んでみてください!
赤本・青本で挫折しないコツ
赤・青は、初期からある何切る本で、いまも「最強クラスの問題集」として評価されています。
ただし、難易度が高く、構成にもクセがあるため、挫折する人も少なくありません。
赤本『麻雀 定石「何切る」301選』
挫折しないためのポイントは、
です。
赤本の目的は、押し引き・定石の判断基準を「なんとなく」から一段深くすることであり、
最初から細部まで暗記する必要はありません。「なんとなく」だと勝つのに限界が来るので、殻を破りたい方は絶対に読むのがおすすめです!
青本『麻雀 傑作「何切る」300選』
青本で挫折しないためには、
くらいの「緩さ」が必要です。
赤・青で多くの人がハマる罠は、
- 正解できない=自分は弱い、と決めつける
- 全問理解しないと先に進んではいけないと思う
この2つです。
ウザク本シリーズは、著者本人も「繰り返し前提」で作っているため、飛ばしながら周回してOKだと割り切った方が、結果的に定着が早くなります。
赤・青まで読み切ったら、麻雀仲間とは差ができて、負けなしになります!勝ち頭に向けて、ぜひ読んでみてください!
他の麻雀本との併用とウザク本の順番に関するQ&A

最後に、ウザク本と他の本・アプリをどう組み合わせるか、そしてよくある「読む順番」に関する疑問に答えます。
他の何切る本との組み合わせ
ウザク本は優秀ですが、「いきなりはキツい」「一度つまずいた」という人も少なくありません。
そんなときに使える「橋渡し本」としては、次のあたりがとても相性が良いです。
たとえば、
というように、ウザク本でつまずいたポイントを、他本で補強するのが効率的です。
ちなみにですが、おすすめの麻雀本15冊を徹底紹介している記事もありますので、もっと強くなりたい方は、ぜひ読んでみてください。
アプリ併用で効率化する方法
ウザク本は書籍だけでなく、スマホアプリ「麻雀ウザク式何切る?」とも連動しています。
アプリ学習のメリットは、下記の点です。
おすすめの使い方は、
- 書籍を1冊通読(ざっくりでOK)
- アプリで「同じテーマの問題」を反復
- もう一度本に戻り、解説をじっくり読み直す
という本⇄アプリの往復学習です。
特に、緑本・金本・赤本の内容をアプリで反復すると、牌効率と押し引きの「反射速度」がかなり上がります。
著者ウザク氏のプロフィール
ウザク氏はペンネーム『G・ウザク』で活動しており、ブログ・note・Xで積極的に情報発信する麻雀研究家。ブログやYouTubeなどのオンラインプラットフォームを通じて、麻雀の研究成果を積極的に公開しています。
特に「何切る問題」の制作数は1,000問を超え、その精緻な問題設計や明快な解説が評価され、多くの麻雀愛好家から支持されています。
さらに、自身の研究成果を活かした書籍の出版やスマートフォン向けアプリ開発にも力を入れており、初心者から上級者まで幅広い層に向けて実践的な麻雀学習コンテンツを提供しています。
ウザク本の順番に関するQ&A
最後に、よくある質問をQ&A形式でまとめます。
Q1. 1冊目に白本と緑本、どっちがいい?
- すでにネット麻雀で何百局も打っていて、ルールも点数計算も問題ないなら、緑本から始めてもOKです。
- 対局経験が少なく、「局の組み立て方」がよく分からないなら、白本を1冊目にする方がスムーズです。
Q2. 白本は「ルール覚えたて」でも読める?
- ルールブックすら読んでいない完全初心者には厳しいです。
- ただし、ルール本を一冊読み、何局か打ったあとなら十分ついていけます。
→ 現実的には「ルール理解済み〜初級者向け」と考えるのが妥当です。
Q3. 赤・青で挫折した。どこに戻ればいい?
- 押し引きや場況判断でつまずいた感覚があるなら、金本や緑本に戻るのがおすすめです。
- 「そもそも形選択が怪しい」と感じるなら、
→ 緑本+他の牌効率本(基本形80など)で、形の基礎から再チェックしましょう。
Q4. 自分の実力より上の巻から始めると何が起こる?
- 解説の半分以上が理解できない
- 正解しても「なぜそれが良いか」を説明できない
- 結果として、実戦でまったく再現できない
という状態に陥ります。
「読んだけど何も変わらない」と感じる最大の原因がこれです。
分からないと感じたら、「一つ前の巻」に素直に戻る方が、トータルでの上達は確実に速くなります。
Q5. ウザク本以外に何を組み合わせればいい?
- 「牌効率」
→ 緑本+平澤牌効率本+基本形80 - 「押し引き・局収支」
→ 赤本+『令和版 現代麻雀 押し引きの教科書』+『現代麻雀 手作りと押し引きの鉄戦術』 - 「弱点補強」
→ 『麻雀 弱点克服ドリル』で、自分の苦手ジャンルをピンポイントで鍛える
このあたりをセットにすると、ウザク本の理解度と実戦への落とし込みが一気に変わります。

ウザク本は、それぞれの巻が「得意分野」を持ってるよ。
自分のレベルより少し下〜ピッタリくらいの巻を選び、分からなくなったら一歩戻る。そして、本で理解したつもりの内容をアプリや実戦で繰り返す。
このサイクルを回せれば、「ウザク本 順番」で迷う時間が、そのまま勝率アップに変わっていくよ。
総括:ウザク本の順番ガイドのまとめ

この記事で整理してきた内容を、最後に要点だけまとめます。
💡ウザク本に関する要点:
この順番ガイドをベースに、「今の自分のレベル+1段階上」のウザク本を1冊選び、まずは1周回してみてください。
分からない箇所が多ければ一歩戻る。理解が物足りなければ次の巻に進む。
そのシンプルな調整こそが、ウザク本を最大限に活かすコツです。




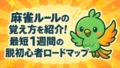

コメント