麻雀の河読みは、相手の打牌傾向から待ち牌や手役、テンパイスピード、さらには狙っている打点までを推測するための重要な技術です。
この記事では、まずスジ読みや壁といった基本的な安全牌の考え方を押さえたうえで、裏スジ・またぎスジ・間四軒など、放銃リスクの高いスジをどう避けるかを具体例とともに解説します。
さらに、手出し・ツモ切りの違いから相手の進行度を読む方法や、瞬時に危険度を判断するチェックリスト、染め手・七対子を読み解いて打点を推測するコツまで幅広く取り上げます。
後半では、放銃ゼロを目指すための守備ルーティンや、リアル卓で活きるしぐさ読み、長期同卓で使える放出傾向の分析といった応用テクニックも紹介。どの章にもすぐ実戦で使えるノウハウが詰まっています。
守備力を高めたい麻雀初心者から、安定した押し引きを目指す中上級者まで、あらゆるレベルの打ち手に役立つ内容です。麻雀の守備は、麻雀の初心者が勝ち方やコツを身に着けていく上で重要な要素なので、ぜひ最後までご覧ください!
麻雀の河読みの基礎とスジ・壁の読みとで守備力アップ!

スジ読みと壁で危険牌を回避
この章では、相手の捨て牌から比較的安全な牌を見抜く基本的な守備術として、スジ読みと壁の考え方を解説します。
スジとは何か、安全度の高いスジ、そして壁やワンチャンスといった補助的な判断基準を組み合わせることで、放銃リスクを抑える手順が身につきます。麻雀初心者でも読みやすい基本からスタートできる内容です。
スジ読みとは?基本の仕組みを理解しよう
スジ読みは、相手の捨て牌から比較的安全な牌を推測する基本的な守備技術です。
例えば、相手が「 」を捨てている場合、「
」を捨てている場合、「 」や「
」や「 」で待つリャンメン待ちの可能性が低くなるため、これらの牌は比較的安全とされます。このような関係を「スジ」と呼び、スジに基づいて安全牌を判断するのがスジ読みです。
」で待つリャンメン待ちの可能性が低くなるため、これらの牌は比較的安全とされます。このような関係を「スジ」と呼び、スジに基づいて安全牌を判断するのがスジ読みです。
スジの基本的な組み合わせは以下の通りです:
これらのスジを覚えることで、相手の捨て牌から安全牌を推測しやすくなります。
このスジというロジックの詳細を理解した方は、フリテンというルールが深く関連しているので、重要なルールなので、ぜひ覚えましょう!
壁・ワンチャンスの考え方
壁(または「ノーチャンス」)は、特定の数牌が4枚すべて見えている(自分の手牌、他家の捨て牌、鳴き牌、ドラ表示牌などで)場合、その牌を含む順子(シュンツ)を他家が作ることができないため、壁の牌に関連するスジも安全とされる考え方です。
例えば、「 」が4枚見えている場合、「
」が4枚見えている場合、「 –
– 」や「
」や「 –
– 」のリャンメン待ちは成立しないため、
」のリャンメン待ちは成立しないため、


 は安全度が高いと判断されます。
は安全度が高いと判断されます。
また、ワンチャンスは、特定の数牌が3枚見えている状況を指し、その牌を含むリャンメン待ちの可能性が低くなるため、比較的安全とされます。ただし、残りの1枚を他家が持っている可能性は否定できないため、ワンチャンスは完全な安全牌ではありません。
安全度の優先順位と注意点
これらの技術を組み合わせて、現物(相手の捨て牌と同じ牌)→壁→ワンチャンス→スジの順に安全度を評価し、放銃のリスクを減らすことができます。麻雀の現物は他記事に詳細にまとめていますので、本記事では、スジ・壁を中心に解説しています。
ただし、これらの読みはリャンメン待ちに対してのみ有効であり、カンチャン待ちやペンチャン待ち、シャンポン待ち、単騎待ちには当てはまらないため、過信は禁物です。
裏スジ・またぎスジ・間四軒(カンスーケン)の注意点
この章では、放銃リスクを抱える裏スジやまたぎスジ、そして複数の裏スジが交差する間四軒の特徴と危険性について学びます。どれも放銃原因として多い形であり、見た目以上に刺さりやすい牌です。具体例を交えて、どのようなパターンが危ないのかを読み解く力を身につけていきます。
裏スジとは?――捨て牌の“隣”が導く危険ライン
裏スジは〈捨て牌の隣にある牌を含むスジ〉を指します。たとえば が捨てられている場合、その隣の
が捨てられている場合、その隣の を起点とする
を起点とする 
 のスジが裏スジになります。
のスジが裏スジになります。
この裏スジという概念は、“読みづらい危険領域”として知られており、特にリーチ直後の選択で多くのプレイヤーを悩ませます。
裏スジが危険視される理由は、たとえば 両面とカンチャンの複合形(例: 

 ) からの手変わりに伴い、裏スジが和了牌になることにあります。
) からの手変わりに伴い、裏スジが和了牌になることにあります。
つまり、リャンメンに向かう途中で不要な隣牌を先に処理するため、あえてその周辺が“河に落ちていても待ちに残る”という構造が生まれやすいのです。
例: が河に切られていた場合
が河に切られていた場合
手牌に 

 とあると、
とあると、  は不要と判断され、切られるケースが多いです。
は不要と判断され、切られるケースが多いです。
そして、 が切られると手牌は
が切られると手牌は 
 のリャンメン形 となり、
のリャンメン形 となり、 の裏スジの
の裏スジの 
 が和了牌になります。
が和了牌になります。
こういった仕組みで裏スジは危険と呼ばれています。
このように、裏スジの待ち牌は、実際には構造上かなり残りやすいことが多いのです。特に序盤に2〜8の中張牌を切ったときの裏スジ は放銃率が上がる傾向が強いので、序盤に切られた中張牌の裏スジには注意が必要です!
またぎスジとは?――“捨て牌を跨ぐ”警戒ライン
またぎスジ(跨ぎスジ)は、河に置かれた数牌を挟む位置にある 4 枚の牌を指します。具体的には、捨て牌 に対して、下記がまたぎスジになります。
 が捨て牌 →
が捨て牌 → 
 のスジがまたぎスジ
のスジがまたぎスジ が捨て牌 →
が捨て牌 → 
 のスジがまたぎスジ
のスジがまたぎスジ
これら 4 枚は左右どちらのリャンメンにも変化しやすく、中盤以降に特に危険度が増すのが特徴です。
例: が河に切られていた場合
が河に切られていた場合


 もしくは
もしくは

 といった形は、牌効率的によく手牌に持たれる形です。
といった形は、牌効率的によく手牌に持たれる形です。
その手牌から、 を切られると、
を切られると、
 もしくは
もしくは
 が和了牌になります。
が和了牌になります。
こういった仕組みで、またぎスジは危険と呼ばれています。
「序盤の裏スジ、中盤のまたぎスジ」と覚えると、実戦でも使えるようになります!
間四軒とは?――裏スジが2本交差する“激アツ”ポイント
間四軒(カンスーケン)は、5差(数が4つ空く)の捨て牌ペアが生み出す、非常に危険度の高い“複合裏スジ”のゾーンです。典型的なパターンは と
と が河にあるケースで、この2牌から裏スジが交差する
が河にあるケースで、この2牌から裏スジが交差する
 のラインが形成されます。
のラインが形成されます。
なぜこれが危険かというと、
 は、
は、
 それぞれ独立して裏スジに該当し、その間の形(
それぞれ独立して裏スジに該当し、その間の形(
 )が構成されている可能性があり、放銃リスクが高いです。
)が構成されている可能性があり、放銃リスクが高いです。
終盤では山に残っている牌も少なくなり、テンパイ形がより狭くなるため、このような“中抜け待ち”や“変則形”が増える傾向があります。
例:
 が河に切られていた場合
が河に切られていた場合



 という形を持っていると、牌効率観点で
という形を持っていると、牌効率観点で 
 を切ることが多いです。
を切ることが多いです。

 が切られると、
が切られると、
 が残り、
が残り、
 が和了牌になります
が和了牌になります
こういった仕組みで間四軒は危険と呼ばれています。
間四軒の配置が見えた時点でその中間牌を切りたくても、勝負手ではない限り、我慢するのが良いです。手出しの変化や相手の構想を読みつつ、慎重な立ち回りが求められます。
手出し・ツモ切りで相手の進行度を予測
ツモ切り=手組みそのまま、手出し=構想変化のサインです! この違いに気づくかどうかで、守備判断の精度がまったく変わってきます。
ツモ切り連打 は、配牌が良好でそのまま進行しているパターンであり、進行スピードが速い=テンパイが近いという警戒ラインにもなります。
また、リーチ直前に突如手出しが混ざる場合、それは“手変わり”を待っていた構想が完了した合図であり、その牌の周辺が牌が非常に危険と認識しましょう。
具体例を挙げると、5巡目までずっとツモ切りだった相手が6巡目に手出しで「 」を切った場合、その周辺の
」を切った場合、その周辺の
 や
や
 のスジが非常に危険です!
のスジが非常に危険です!
このように、手出しとツモ切りの流れから相手のテンパイスピードや狙いの方向性を推測できるようになると、リーチ宣言牌の安全度を事前に逆算することも可能になります。テンパイスピードに応じた守備選択をすることで、放銃を1局ごとに減らしていくことができるのです!
麻雀の河読みで危険牌を避ける実戦テクニック

危険牌・安全牌を瞬時に判断するチェックリスト
👇 放銃回避フロー(捨てたい牌が当たるか迷ったら上から順にチェック!)
- 現物か? → YESなら切る。まずは相手がすでに切っている牌=絶対安全。基本中の基本!
- 4枚見えの壁か? → YESならほぼ安全。完全壁の牌は順子が成立しないので、リャンメン待ちにも対応できません。
- 表スジ・ワンチャンスか? → 安全度中。ある程度は信用できるが、カンチャンやシャンポンには当たる可能性があるので注意。
- 裏スジ・またぎスジ・間四軒か? → 危険度高。これらは見た目以上に放銃率が高く、リーチ後に不用意に切ると手痛い一打になりがち。
- ノーチャンス・色が被るか? → 最危険! 河にも自分の手牌にもない色は相手の染め手リスクが急上昇。特に終盤は要警戒!
✅ このフローを使えば、難解な場面でも瞬時に安全度をランク分けできます。スマホにメモしておけば実戦でも即活用可能!
もし、放銃回避を上達したければ、牌読みのアプリ・ツールを活用することをおすすめします。
天鳳位ヨーテル氏が書いた「麻雀・捨て牌読みの傾向と対策」という書籍が非常に実用的であるため、河読みの麻雀戦術本としておすすめです。
染め手読みと七対子読みで打点を推測
色バラ切り→同色連打は ホンイツ警戒シグナル! 特に、序盤に2色以上の牌を雑に捨てた後、中盤以降で一色に寄せるような動きが見えた場合は要注意です。
これはホンイツ(混一色)を狙っている典型的な流れで、相手の打点が跳ね上がっている可能性があります。ホンイツは鳴いても成立する役なので、速攻で仕上がるケースも多く、早めの対応が必要です。
また、序盤から中張牌の打牌が目立つなら 七対子 を疑いましょう。七対子は手牌の形から読みづらく、特に同じ牌を2枚ずつ持つために字牌や端牌を多く抱えがちです。そのため、字牌単騎・端牌単騎 が多くなり、普段は安全牌と見なされる牌が危険になることも少なくありません。
こうした情報から打点推測ができれば、「この放銃は9600点? それとも跳満?」といったリスクの見積もりができ、押し引き判断もより明確になります。状況に応じて、安い放銃で済むなら押す、高打点が見えたらベタオリ、といった判断ができるようになれば、一段階上の守備力が手に入ります。
放銃ゼロを目指す麻雀初心者の守備手順
下記の手順により、放銃率を下げるような立ち回りができるようになるため、放銃率が高くて悩んでいる方は、ぜひ実践してみてください!
- 現物プラス1枚 を常備する意識で牌を抱える。リーチが入る前提で安全牌を常に1〜2枚持っておくと、いざという時に慌てず対応できます。理想は現物+壁牌またはワンチャンス牌の組み合わせです。
- リーチ宣言から2巡は完全ベタオリを徹底。特にリーチ直後は相手が押し気味なことが多く、手出し情報も乏しいため、安全第一で現物・壁牌を優先的に切りましょう。
- 巡目が深くなったら 壁+ワンチャンス でギリギリまで粘る。終盤では現物が尽きるケースもあるため、4枚見えの壁牌、3枚見えのワンチャンス牌を組み合わせて放銃率を抑える選択が必要になります。必要ならリャンメン以外の待ち(裏スジやカンチャン)もケア対象に。
- オーラスは点数状況優先で押し引きを再計算。自分がトップ目・ラス目かどうかで戦略は変わります。たとえ危険牌であっても、逆転条件を満たすためには押すべき局面もあるので、スコアを見ながら判断を!
守備手順は“読み”というより“体に染み込ませるリズム”です。ルーティン化すれば局ごとの判断時間が短くなり、迷いが減り、自然と放銃率が激減していきますよ!
麻雀の河読みを極める応用&人読み
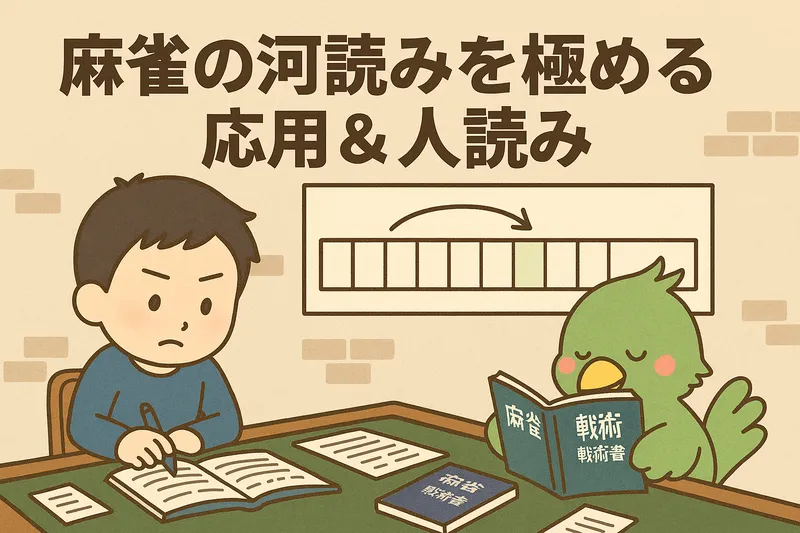
打牌スピードとしぐさを組み合わせた多層解析
リアル卓限定ですが、ツモ動作が遅い=多面張選択で迷い、強打=ドラ複数保持 といった“動作テレグラム”は確かに存在します。こうしたしぐさから得られる情報は、相手の手牌構成や心境を探る上で貴重なヒントになります。
たとえば、ツモ牌を少し長く見つめてから切る場合は、手牌構成が複雑(多面張)で選択肢が多く、最も効率的な切り方を精査しているサインかもしれません。
また、牌を強く打つ場合は、ドラを複数抱えている、あるいは役満や倍満といった高打点の手をテンパイしていて自信があるケースが多いとされます。ただし、これらの情報は人によるクセや性格にも左右されるため、あくまで“参考材料”として扱うべきです。
特にオンライン麻雀では、こうしたしぐさ情報は一切得られないため、河読みや牌理の補助情報としての位置づけにとどめておきましょう。逆にリアル卓では、プロの実戦動画やMリーグなどの映像を視聴して“動作から読み取れるパターン”をメモしておくと、実践でも読みの精度が飛躍的に上がりますよ!
放出傾向読みで相手のクセを掴む方法
長期同卓では「役牌を早切りする派」「萬子嫌い」「1索だけ妙に遅く出る」といった放出傾向が徐々に浮き彫りになってきます。
こうした傾向を見逃さずに拾っていくことで、相手の牌選びや手組みのクセが手に取るようにわかってきます。特に、連戦が前提の雀荘やネット対戦で同卓率が高い相手には非常に有効です。
こうした“人読み”を実践することで、驚くほど刺さるリーチ回避や押し引き判断が可能になります。長期同卓の場合は、1人1人の打ち方の傾向を把握していくことが、長期的な勝率アップに繋がっていきます!
麻雀の河読みまとめと上達ロードマップ
▼この記事のポイントまとめ


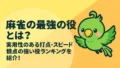

コメント