麻雀は運のゲームに見えますが、長い目で見ると「毎局の選択の質」で差がつきます。
だからこそ、学ぶ順番がとても大事です。
本記事では、初心者〜中級者が麻雀の効率的な上達を求めている方向けに、最短で伸びるロードマップを整理します。
💡この記事で理解できるポイント
- 麻雀が「うまくなる」の正体
- 最短で伸びる学習順
- 何切るの迷いを減らす牌効率の骨格
- 放銃を減らす守備の基準と、ベタオリの捨て順
麻雀うまくなるには?上達の基本

最初に結論です。
麻雀がうまくなる近道は、闇雲に打つことではありません。
「伸びやすい順」に、土台から積むことです。
麻雀における上達の定義と優先
「麻雀がうまい」は、派手な読みが当たることではありません。
結局プレイヤーができるのは、打牌・鳴き・リーチなどの選択だけです。
その選択が、毎回、ある程度良い選択で同じ基準でできる状態が「上達」です。
短期の勝ち負けはブレます。
でも、良い選択を積み重ねる人は、長期で成績が安定します。
学ぶ優先順位は次の流れが強いです。
- まず手を進める「牌効率」。
- 次に段位戦で大事故を避ける「守備」。
- そのあとに、押し引き、終盤の「点差感覚」や応用(鳴き・読み)です。
牌効率を最優先
牌効率は「なるべく無駄なく、速くテンパイに近づくための捨て牌選択」です。
脱初心者が一番伸びるのはここです。
理由は単純で、牌効率は「毎局ほぼ必ず勝つために重要な要素」だからです。
逆に読みや高度な駆け引きは、そもそも前提が多く難しいです。
最低限、ここだけ押さえると迷いが減ります。
- シャンテン数(テンパイまで何回変化が必要か)をざっくり把握する。
- 5ブロック(面子候補を5つ作る意識)で手牌を整理する。
そして、受け入れが広い形=両面を大事にします。
たとえば孤立牌は、字牌や1・9が弱く、4〜6が強いです。
「次に来て嬉しい牌が多いほう」を残すからです。
迷ったら、字牌→端寄り→真ん中寄りの順で切るだけでも、聴牌効率は高まりますので、覚えておきましょう!
牌効率もっと詳しく知りたい方は、「牌効率の基礎、応用、勉強方法を整理した記事」がありますため、詳細はそちらをご覧ください。
牌効率は我流でやってこられた方だと、意外と基礎ができていない方が多いため、これを機に勉強してみてください。
守備で放銃減らす
勝てない原因は「アガれない」より「振り込みで壊れる」ことが多いです。
1局で自分がアガれる確率は高くありません。
だから、アガれない局に点を守れる人が、段位戦で強いです。
守備の核は、読みではなくベタオリ(徹底して降りる)です。
中途半端に押して、結局放銃するのが一番損です。
特に雀魂等のネット麻雀の段位戦は、得点より順位が大事です。
4位のマイナスが重いので、放銃を減らすだけで成績が上がりやすいです
守備についてもっと詳しく知りたい方は「麻雀における守備の重要性・戦術・勉強方法をまとめた記事」がありますため、ご覧ください。
守備に関する基礎、戦術を網羅的にまとめているため、放縦率を改善したい方に役立つ情報ばかりです。

最短で伸びる人は「牌効率でテンパイを増やし、守備でラスを減らす」を先に固めるタイプだよ。
地味かもしれないけど、最重要要素だから、ぜひ鍛えてください!。
麻雀うまくなるには?てりやき流の実戦判断を3つ紹介

ここからは対局中の判断を、迷いにくい「軸」にして整理します。
牌効率だけ知っていても、実戦はリーチや点差でブレやすいからです。
何切るの軸を作る
何切るで迷うときは、判断軸が増えすぎています。
まずは「テンパイまで最短」を優先して、型を固定すると速くなります。
軸は次の2つで十分です。
- 1つ目はシャンテン数です。テンパイに近いほど価値が高いです。
- 2つ目は受け入れです。次に良い形になる牌が多い方を残します。
そのために便利なのが5ブロックです。
手牌を「面子になりやすい塊」として見ます。
対子を抱えすぎると受け入れが狭くなりやすいので、まずは対子は2つ程度の意識でOKです。
また、牌の形も重要です。
たとえば「
 」と「
」と「
 」で迷ったら、基本は
」で迷ったら、基本は
 を切りやすいです。
を切りやすいです。

 は
は を引いて両面になれる伸びしろがあるからです。
を引いて両面になれる伸びしろがあるからです。
こういう「形の強弱」を覚えるほど、瞬時に良い判断ができるようになります。
こちらも牌効率の内容なため、もっと学びたい方は牌効率の記事をご覧ください。
リーチ押し引き基準
押し引きの上達で大事なのは、他家の手牌や河読みよりも押し引き基準を構築することです。
まず警戒サインを決めて、毎回同じ順で考えます。
初心者〜中級の基準として分かりやすいのはこれです。
警戒サインの例
- 他家からリーチされる
- 他家が2回以上鳴く
※要は誰かが聴牌したら、もしくは聴牌気配を感じたら、押し引きを検討するというためのサインです
この警戒サインが発生したら、自分の進み具合(シャンテン)と打点見込みを見て押し引きを決めます。
押し引きの目安
- テンパイ:基本は押し(ただし待ちが弱すぎる等は例外)
- 1シャンテン:3翻以上見込めるなら押し寄り、2翻以下なら降り寄り
- 2シャンテン以上:基本はオリ(例外は終盤の条件戦くらい)
押し引きにおいて、もう一つ大事なのは、「降りると決めたら、回し打ちよりベタオリを優先」ということです。
中途半端な「ちょっとだけ押す」が一番事故ります。
押し引きの基準・表や勉強方法を他記事にまとめているため、もっと詳しく学びたい方はぜひご覧ください。
点差とオーラス判断
麻雀の長期的な勝敗(特に雀魂などのネット麻雀の段位戦)は「得点」より「順位」で決まることが多いです。
特に4位のマイナスが重いので、ラス回避が最優先になります。
終盤は「今アガる」より「何位で終わるか」で価値が変わります。
例えば、4位で大きく離されているなら、1000点アガっても順位が変わりません。
この場合は、鳴いて安くするより、逆転条件を満たす手を作る方が筋が通ります。
点差判断の注意点もあります。
点差=必要打点が常に一致するわけではありません。
- ロンなら直撃かどうかで差が大きく変わる
- ツモは支払いが分散し、親子で点数の縮まり方が異なる
つまり、オーラスは「誰からロンするか」「ツモか」で逆転条件が必要打点が変わるということです。
下記のようにツモ、ロンで縮む点差を頭に入れておくと、判断が早くなって、目指す手牌の形を考えられるようになります。
| 打点 | ツモで縮む点差 | ロンで縮む点差 |
|---|---|---|
| 満貫(8,000点) | 親:12,000点 子:10,000点 | ロンされた人:16,000点 ロンされてない人:8,000点 |
| 跳満(12,000点) | 親:18,000点 子:15,000点 | ロンされた人:24,000点 ロンされてない人:12,000点 |
| 倍満(16,000点) | 親:24,000点 子:20,000点 | ロンされた人:32,000点 ロンされてない人:16,000点 |
最低限、この3つは覚えておきましょう。

戦で勝敗を分けるのは「迷う場面でも良い選択をブレずに決めれる」ことだよ。
何切るは牌効率、リーチは押し引き、終盤は順位と条件を先に見るだけでも、かなり安定した麻雀になるよ。
これらを基準に実践していって、自分の麻雀スタイルを調整していくと、もっと楽しくなっていくよ!
麻雀うまくなるには?練習法・おすすめ麻雀本・Q&A

上達は「分かったつもり」では進みにくいです。
学んだことを、問題→言語化→検討→反復で体に入れるのが近道です。
麻雀うまくなるにはの練習法
おすすめは「ただ打つ」以外の練習を少し混ぜることです。
最も効果的なのは、次の流れを繰り返し、自身の麻雀をどんどん改善していくことです。
- 自分の弱みを把握する(雀魂牌譜屋を使うと効果的)
- それに関連する麻雀本を読む
- 雀魂等のネット麻雀で実践する
麻雀本はプロもしくはプロ級の人たちのノウハウが詰まっているため、その考えを取り入れると爆発的に麻雀はうまくなっていきます。
牌効率、守備、押し引き、鳴きの4つが麻雀で重要な要素なため、それらの人気&おすすめ本を紹介しますので、ぜひ読んでみてください。
また、実戦も、打ちっぱなしより牌譜検討が伸びます。
「迷った瞬間」を見返して調べると、記憶に残りやすいです。
雀魂のリプレイや麻雀AIのMortalは、この用途にかなり向いています。
麻雀AIのMortalの使い方や見方について、他記事にまとめているため、そちらをご覧ください。
また、次に効く方法は、次の流れで復習するやり方です。
- 何切る問題を解く(時間を決めて1問30〜60秒)
- 自分の答えの理由を1行で言語化する
- 解説でズレを確認し、ズレた原因を1つだけ特定する
- 似た形を翌日もう一度解いて、同じミスを潰す
上記の方法で細かい基準を調整できるため、麻雀本を読む→実戦のサイクルと並行すると、もっと効果的です。
麻雀がうまくなるために効果的な麻雀本
本は「今の一番の弱点」を埋めるのに強いです。
牌効率で迷う人、放銃が多い人、鳴きが苦手な人で、選ぶべき本が変わります。
ここでは目的別に、評価が高く実戦に効きやすい4冊を紹介します。
牌効率のおすすめ本:麻雀 定石「何切る」301選
📘 概要
実戦的な牌姿301問で、「受け入れ枚数」だけでなく打点や期待値まで含めた何切るを学べる問題集です。
複合形(4連形・中ぶくれ・多面待ちなど)の優劣が整理されていて、形の見え方が変わります。
🌟 特徴
- 受け入れ+手役(例:三色・一盃口)も含めた期待値思考を鍛えられる
- よく出る複合形を「パターン」として覚えやすい
- 解説が具体的で、迷いがちな選択の理由が分かる
👤 口コミ
- 複合形の強さが理解できて、形の見え方が変わった
- テンパイ速度だけではない“得な一打”が分かった
- 難しいが、身につけば確実に強くなるタイプ
実戦頻度の高い手牌に絞って解説しているため、効率的に定石を身につけられると人気の高い一冊です。特に中級者が次のステップへ進む際の教材として非常に適しており、繰り返し解くことで自然と判断基準が定着しやすい構成になっています。
また、解説は無駄が少なく簡潔で、問題を解き進めるごとに自分の打ち筋を客観的に検証できる点も大きな強みです。さらに301問というボリュームがあるため多様なパターンに触れることができ、実戦で遭遇するケースへの対応力が着実に養われます。
読み進めるごとに学習効果を実感しやすく、総合的に見ても中級者がさらなる飛躍を目指すうえで心強い学習教材といえるでしょう。

何切るの“形の判断”で止まる人は、この1冊で一気に改善できるよ。
単純な牌効率、打点を加味した牌効率を学べるため、ぜひ和了率、平均打点に困っている方は読んでみてね!
kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!
➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!
牌効率のおすすめ本:現代麻雀技術論
📘 概要
統計・シミュレーター寄りの考え方で、牌効率から押し引き、オーラス判断までを広く扱う総合教科書です。
情報量が多く、「戦術辞典」に近いタイプの一冊です。
🌟 特徴
- 1シャンテン/2シャンテンの手組みが細かく整理されている
- リーチ判断、ベタオリ、回し打ちなど実戦判断も体系的
- 牌姿例が多く、辞書的に調べ学習しやすい
👤 口コミ
- 現代麻雀の教科書。基礎を固めるなら避けて通れない
- 濃すぎるが、必要な所だけでも読むと迷いが減る
- 牌姿が多くて理解しやすい
この本は、「なんとなく打っている」状態から抜けたい人に強くおすすめです。
『現代麻雀技術論(令和版)』は、統計やシミュレーターに裏付けられた“現代麻雀の標準”を一冊に凝縮した総合教科書です。
牌効率と押し引きを核に、1・2シャンテンの手組み、鳴き判断、ベタオリ/回し打ち、さらにはオーラスの点数状況判断まで、勝敗に直結する技術を体系的に学べます。最大の魅力は、圧倒的な牌姿例と「図のすぐ上に解説」という分かりやすい構成。
迷いやすい例外や微妙な選択も注釈で拾ってくれるので、感覚頼りの打牌が“理由のある一打”に変わります。全部を暗記する本ではなく、必要なパターンを辞典のように引けるのも強み。
ネット麻雀でもフリーでも「何を切るか」「押すか降りるか」で迷いがちな人ほど、判断軸ができて成績が安定していきます。読むだけで得るものが大きい、土台作りの決定版です。

麻雀は確率のゲームだから、統計データでの鍛え方はかなり効率的だよ。
周りの雀士より一歩強くなりたい方や、我流麻雀に限界を感じている方に最適な本だから、絶対に読んでみてね!
kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!
➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!
守備のおすすめ本:守備の教科書
📘 概要
放銃を減らすための守備を、現物・スジなど基礎からベタオリ、押し引きまでまとめた「守備特化本」です。
章末に確認問題があり、守備を型として身につけやすい構成です。
🌟 特徴
- 現物/スジ/ノーチャンスなど基礎を丁寧に整理
- ベタオリを「勝つための戦術」として扱う
- リーチ・鳴きへの対応まで一通り触れる
👤 口コミ
- 放銃が多い人にちょうどいい。体系的で分かりやすい
- 基礎とベタオリだけでも成績が安定した
- 後半は難しいが、考え方が分かるだけで得
井出洋介×小林剛という、スタイルの違うトッププロ2人が「守備」に特化してまとめた一冊です。
攻撃寄りの人も守備寄りの人も、共通して押さえるべき守備技術が整理されています。
- 放銃が多くてラスが多い
- なんとなくスジ読みで凌いでいる
という悩みを、体系的な守備理論で解決してくれます。
現物・スジ・ノーチャンスから、ベタオリ手順、リーチ・鳴きへの対応まで、守備の全体像が一冊でつながります。
この本を通して、次のような状態が目指せます。
- 明らかな放銃を大きく減らせる
- ベタオリの基準と手順がはっきりし、「中途半端に押して大きく振る」が減る
- 捨て牌や鳴きから危険牌を読めるようになり、「理由を持って降りる」感覚が身につく
各章末に「おさらいドリル」があり、読んだ内容をすぐに問題で確認できます。
レビューでも「守備入門として最適」「基礎固めにちょうどいい」という声が多く、初〜中級への橋渡し本として評価が高いです。
ルールと役を理解していて、「そろそろ守備を本気で固めたい」と感じているなら、まずこの一冊から始めてみてください。
迷ったら「守備の教科書」を一通り読み込み、気になる章のおさらいドリルを3周することをおすすめします

麻雀がうまくなるには、アガるよりも、放銃しないスキルを身に着ける必要があるよ。
大体、麻雀で負けるときは守備が上手くいっていない時だよ。だから、安定して勝てるようになりたい方はこの本を必ず読んでね!
kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!
➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!
鳴きのおすすめ本:勝ち組の鳴きテクニック
📘 概要
鳴きをテーマにしつつ、実戦の“勝ち筋”を増やす細かいテクニックが多い中上級者向けの本です。
特にアガリトップ条件や、形式テンパイ絡みの判断が多めです。
🌟 特徴
- 速度だけでなく、守備や場況も含めた鳴きが学べる
- ブラフ鳴き、鳴かせ、絞りなど発想の引き出しが増える
- マニアックだが実戦で刺さる局面がある
👤 口コミ
- 中級以上なら確実に得るものがある
- 鳴きの発想がアップデートされた
- 全部を鵜呑みにせず、合う所だけ吸収が良い
鳴き判断を体系的に鍛えたい方に最適な一冊です。各章は実戦図→解説→練習問題の流れで構成され、鳴くべきか否かの基準を場況・点棒状況・手組の速度など複数の観点から多角的に示してくれます。
具体的には、リーチを受けた際に速度を優先すべきか安全度を重視すべきか、トップ目とラス目では同じ鳴きでも意味合いが変わるなど、局面ごとの具体的な思考法を学べるのが大きな魅力です。
また、強引クイタンや役なしポン、海底回しチーといった実戦テクニックも扱い、攻撃力が増す場面と守備が薄くなる場面を比較しながら、状況判断を一層磨ける構成になっています。
さらに押し引きとの兼ね合いを意識しながら副露精度を高められるため、「不用意な副露が減った」「アガリに繋がる鳴きだけ選べるようになった」「勝負所での判断に迷わなくなった」といった声も多く寄せられる実用度の高い一冊です。

鳴き麻雀で天鳳9段まで行った川村プロの麻雀本だよ。
特に和了率が低い方や、鳴いてよく放銃する方には、かなりおすすめだよ!
kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!
➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!
麻雀うまくなるにはQ&Aと総括
Q1. リーチとダマテンは結局どっちが正解ですか?
基本はリーチでOKです。
リーチは打点が上がり、相手を降ろせる効果もあります。
ただしオーラス僅差で供託が順位に影響する時や、手替わり価値が高い時はダマも候補です。
万能解ではなく「点差・終盤・手替わり」で使い分けるのが前提です。
Q2. 鳴いた方が勝てますか?
鳴きは速度が出ますが、守備力が落ちます。
「速いアガリが見える」か「高打点が見える」時に絞ると失敗が減ります。
中途半端な鳴きは、押し返された時に損が出やすいです。
Q3. 点数計算は全部覚える必要がありますか?
基本的は細かい条件戦を判断するために必要です。
ただし、まだ覚えていないという方は、満貫以上のゾーンと、オーラスで「誰から上がると逆転か」を見る習慣が先です。
点差表示がある環境では、条件確認の方が実戦的です。
麻雀うまくなるには?最短上達のための総括

💡麻雀がうまくなるためのまとめ:
- 麻雀がうまくなるとは、運ではなく毎局の選択の質を上げることです
- 最短の学習順は、牌効率→段位戦(順位)→守備→点差感覚→応用です
- 牌効率は「シャンテン数」と「受け入れ」の2軸で迷いが減ります
- 5ブロックで手牌を整理し、両面になりやすい形を残すのが土台です
- 守備は読みよりベタオリが先で、中途半端な押しが最大の失点源です
- ベタオリは「合わせ打ち→現物→複数に通る安全牌→相対安全」の順で考えると安定します
- 雀魂段位戦は得点より順位が重要で、特にラス回避が成績を決めます
- 点差と必要打点は一致しないことがあり、オーラスは「誰から/ツモか」まで確認します
- リーチ/ダマ、鳴きは条件次第で正解が変わるため、基準を作って使い分けます
- 上達の核は、何切る→理由の言語化→牌譜検討→反復のループです

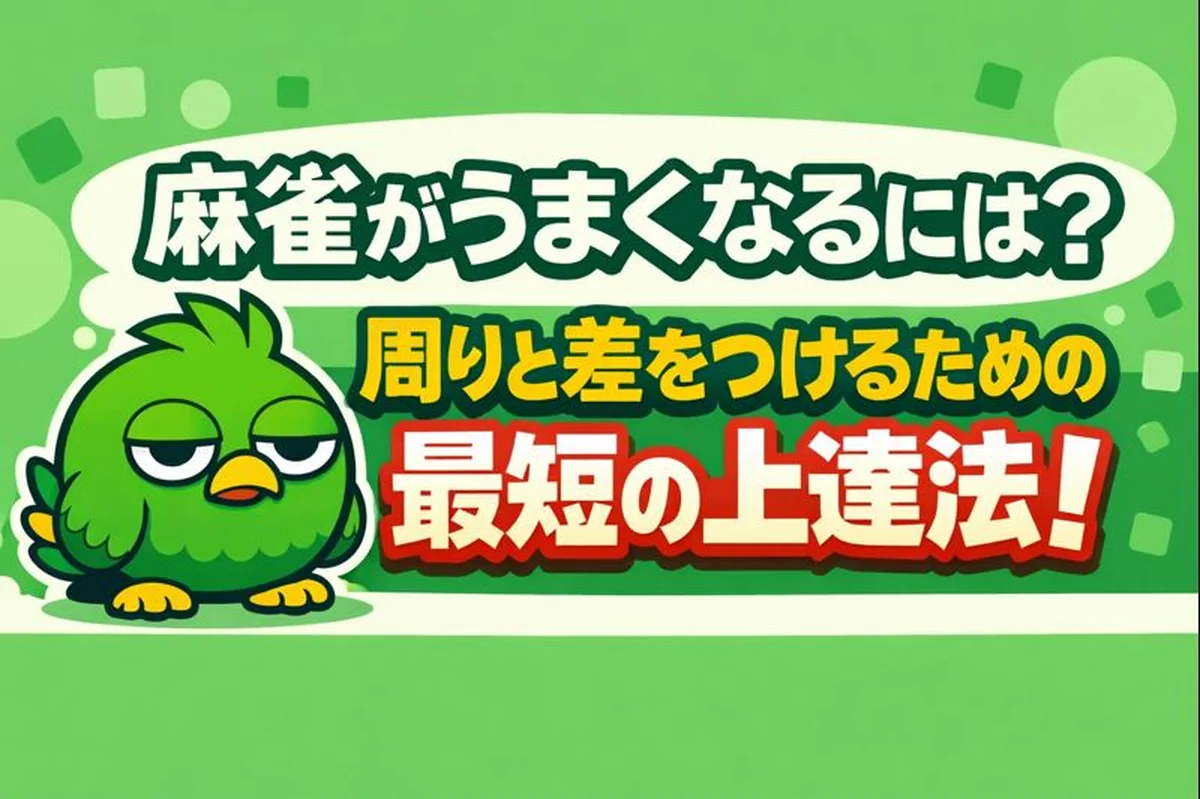

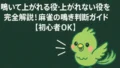
コメント