麻雀プロの年収は幅が広く、生活の安定度は人によって大きく異なります。本記事では、平均年収の目安やMリーガーと一般プロとの収入差、さらに上位プロ雀士の具体的な年収レンジを紹介します。
加えて、対局料や解説料、イベント出演料、スポンサー契約など収入源の内訳を詳しく説明し、資格だけでは収入にならない現実や低年収が多い理由も取り上げます。また、配信・出版・解説など収入を得やすい活動や副業・会社員との両立方法、実際の生活モデルをもとにした収入戦略も解説します。
最後に、収入を伸ばすためのステップや志望者へのアドバイスを提示し、麻雀プロの年収について総合的な理解が得られるように構成しています。
💡この記事のポイント
- 麻雀プロ全体の平均年収や、Mリーガーとの大きな収入差がわかる。
- 上位プロ雀士の具体的な年収レンジや高収入事例を知ることができる。
- 麻雀プロの収入源の内訳や資格だけでは収入にならない現実を理解できる。
- 副業や配信活動を含めた収入を伸ばすための戦略と志望者へのアドバイスを学べる。
本記事は麻雀プロの年収に関する記事ですが、そもそも「麻雀プロになるには?」という疑問の方向けの記事もあるため、ぜひ併せてご覧ください!
麻雀プロの年収と収入源の基本

平均年収の目安と一般プロとMリーグ所属プロの違い
一般的な麻雀プロの年収はおおよそ200万〜300万円台と言われており、多くの場合は雀荘での勤務収入に大きく依存しています。雀荘スタッフとしての給料は決して高い水準ではなく、生活費をぎりぎり賄える程度にとどまることが多いのが現実です。
また、勤務時間が不規則になりやすいため、安定した生活を送るには厳しい一面もあります。その一方で、プロリーグであるMリーグに所属している選手は最低保証年俸400万円が設定されており、さらに成績や知名度に応じて解説やイベント出演の収入が上乗せされます。
さらにスポンサー契約や配信活動によって追加の収入を得るケースも多く、Mリーガーはより多角的な収益モデルを構築できるのです。Mリーガーの平均的な年収は500万〜1,000万円程度と推定され、安定しており、一般プロとの差は歴然です。
つまり、Mリーガーと一般プロの収入差は非常に大きく、生活の安定度だけでなく将来的なキャリアの展望や活動の自由度にも大きな違いを生み出していると言えるでしょう。
※Mリーガーの推定年収ランキングも気になる方はぜひご覧ください!
上位プロの年収レンジと年収が高い雀士の具体例
トップ層のMリーガーや有名解説者は年収1,000万〜1,500万円に達する例もあり、一般的なプロとは全く異なる収入水準を誇ります。例えば、佐々木寿人選手は「日平均年収が満貫だとしたら三倍満か役満くらい」と発言しており、その活躍ぶりからも高収入が現実であることがうかがえます。
また、岡田紗佳さんや長澤茉里奈さんのように1,000万円以上を稼いでいると言われている女性プロも存在し、メディア露出やタレント活動と麻雀を組み合わせて成功している点が特徴です。さらに、多井隆晴選手や堀慎吾選手のようにトップ成績を維持し続けるプロは、解説やスポンサー契約を含めて数千万円規模の収入を得ていると推測されています。
このような事例は確かに華やかですが、プロ人口の中ではごくわずかであり、こうした成功は例外的なケースであることを理解しておく必要があります。多くのプロにとっては夢のような数字であり、現実的には努力や工夫を重ねても到達が難しい水準だという点を強調しておくことが大切です。
対局料・解説料・イベント出演料・スポンサー契約など収入源の内訳
麻雀プロの収入は多岐にわたります。雀荘勤務や教室の講師料、雑誌や書籍の印税、テレビやイベント出演料、さらにYouTube配信やスポンサー契約など、多様な分野に広がっています。
中でも雀荘での勤務は多くのプロにとって生活の柱となり、講師活動や出版物による印税収入も補助的な役割を果たします。また、テレビやネット番組の解説出演は一度の出演でまとまった収入になる場合があり、知名度を高める機会にもつながります。
しかし、大会の賞金はJPML公式一覧に基づき100万円前後中心で、それを超える大会もありますが、生活を賄うには十分ではありません。つまり、賞金だけで生活を維持するのは現実的に難しいのです。
そのため、多くのプロは複数の収入源を掛け合わせて生計を立て、配信活動やスポンサー契約によってさらに収入の幅を広げようとしています。こうした多角的な収益モデルを築くことが、麻雀プロとして継続的に活動するための大切なポイントなのです。
麻雀プロの年収の実態と今後の展望

プロ資格だけを持つ場合の収入の有無と低収入が多い理由
麻雀団体に所属しても団体から直接給料が支払われることはなく、麻雀プロの資格だけを取得したとしても自身で活動をしなければ収入を得ることはできません。
日本全国にはおよそ3,000人ものプロ雀士が存在すると言われていますが、その中で大会の賞金だけで生活を成り立たせられるのはほんの一握りに過ぎません。
むしろ多くのプロは、雀荘勤務での給料やイベントの出演料、さらにはアルバイトや会社員としての仕事を組み合わせて収入を補っています。中には配信活動や個別レッスンなどを副収入として取り入れる人もおり、ようやく生活が成り立つというのが現実です。
このように、プロ資格だけでは経済的な自立は困難であり、複数の手段を活用して生計を立てる必要があるのです。
配信・出版・解説など収入を得やすい活動と副業や会社員との両立
最近はYouTube配信やSNSを活用して広告収益や投げ銭を得るプロも増えており、動画の企画や解説配信を通じてファン層を広げています。また、麻雀技術に関する書籍執筆や雑誌記事の寄稿、さらには大会やイベントでの解説業務なども収入を得やすい活動として人気があります。
さらに、オンライン講座や個別指導といった教育的なサービスを副収入として展開する人も増えてきました。とはいえ、多くのプロは会社員として本業を持ちながら麻雀活動を続けており、休日や仕事終わりの時間を活用して兼業の形で収入を補っています。
このような多角的な取り組みが、プロとして活動を続ける上での現実的な選択肢となっているのです。
実際の生活モデルと収入を伸ばすための戦略
例えば、雀荘勤務で月20万円前後、解説やイベントで追加の10万円、さらにYouTube配信で数万円という収入モデルが一般的に考えられます。これを毎月積み重ねることで、年間の合計収入は400万円台に届くケースもあります。
さらにここに個別レッスンや麻雀教室での講師料、雑誌への寄稿やメディア出演料などを組み合わせれば、もう一段階高い収入水準に達する可能性も出てきます。つまり、ひとつの収入源に依存せず、いくつもの活動を同時に展開することが安定した収入につながるのです。
収入を伸ばすためには、多様な収入源を確保するとともに、自身の知名度やブランド力を高めていく努力が肝心であり、その積み重ねが将来的な安定にもつながっていきます。
麻雀プロの年収を踏まえた麻雀プロ志望者へのアドバイスとQ&A

麻雀プロの年収を踏まえた志望者へのアドバイス
麻雀プロを目指すなら、まず収入面での厳しさをしっかり理解したうえで挑戦することがとても重要です。雀荘での勤務やゲスト出演、さらに配信活動やイベント解説などを組み合わせ、複数の収入源を確保する姿勢が求められます。
プロ資格はあくまで出発点にすぎず、それ自体では収入を生まないため、成功には実力と発信力の両方を磨いていく努力が必要です。さらに、知名度を上げる工夫やスポンサーを獲得するための活動も不可欠であり、地道な積み重ねが将来的な安定につながります。
麻雀プロの年収は夢と現実の両方を映し出すものであり、その中で自分がどのようにキャリアを築き、長期的に活動を続けていくのかが大切だといえるでしょう。
麻雀プロの年収に関するよくある質問(Q&A)
Q. 麻雀プロは資格を取れば収入が得られますか?
A. プロ資格だけでは収入は発生せず、雀荘勤務や配信活動などを通じて収益を得る必要があります。
Q. Mリーガーと一般プロの収入差はどれくらいですか?
A. 一般プロは年収200万〜300万円台が多いのに対し、Mリーガーは最低400万円から平均500万〜1,000万円と大きな差があります。
Q. 麻雀プロで安定して生活するにはどうすればいいですか?
A. 雀荘勤務に加えて解説、イベント出演、配信など複数の収入源を組み合わせることが安定につながります。
Q. 大会賞金だけで生活することは可能ですか?
A. タイトル戦の優勝賞金は大会によって幅があり、JPML公式一覧でも100万円前後が中心だが、それを上回る大会もある。なおMリーグはチーム優勝5,000万円(チーム賞金)。
Q. 麻雀プロとして収入を伸ばすには何が重要ですか?
A. 実力を磨くだけでなく、知名度を高めて配信やスポンサー契約を得るなど、多角的に活動を広げることが収入増加のカギです。


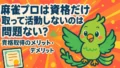
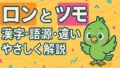
コメント