麻雀プロになるには、受験資格や試験内容の理解から始まり、合格後の活動や収入の実情を知ることが欠かせません。本記事では、年齢制限や合格率、主要団体の特徴や選び方、さらにリーグ戦・解説・配信活動などプロとしての仕事内容までを網羅的に解説します。
メリットや厳しさ、Mリーグをはじめとした最新トレンド、地方対応や発信力の重要性、さらには非プロでも活躍できる選択肢までを含め、麻雀プロを目指す方に必要な情報を整理しました。
💡この記事のポイント
- 麻雀プロになるための条件や受験資格、試験内容を理解できる。
- 団体ごとの特色や活動方針の違いを比較して把握できる。
- プロになった後の活動内容や収入源の実情を知ることができる。
- メリットとデメリット、そして非プロでも活躍できる道を理解できる。
麻雀プロになるには知っておきたい基本の条件と流れ

麻雀プロを目指すには、まず18歳以上であることが条件です。また、高校生は受験できず、社会人や学生が対象となります。
試験は書類・筆記・実技・面接が中心で、点数計算やマナーが重視されます。つまり基礎を習得し、長期的に努力を続ける姿勢が必要です。
年齢制限や受験資格の基準
麻雀プロ試験の多くは、「18歳以上・高校生不可」という受験の条件があります。これは学業との両立や未成年者の責任能力を考慮しての規定であり、社会的な信頼を前提とするプロ活動には妥当な条件と言えるでしょう。
また日本プロ麻雀連盟では40歳未満という年齢制限が設けられており、若手を積極的に育成して将来的に長く活躍できる人材を確保する方針が見られます。
とはいえ、最高位戦や協会、RMUといった団体には年齢制限が存在せず、社会人や中高年からでも新たな挑戦を受け入れる柔軟さがあります。実際に定年後に趣味から転じて受験する方や、学生時代に麻雀を覚えて社会経験を積んだ後に改めて挑戦する方も多く、門戸は幅広く開かれているのです。
プロ試験の内容と合格率の目安
試験内容は団体ごとに異なりますが、共通して点数計算や対局マナーの確認が非常に重視されます。筆記試験では基本的な点数計算問題から条件付きの応用問題まで幅広く出題され、単に正解するだけでなく正確さとスピードが求められます。
実技試験では数半荘を打ち、勝敗そのものよりも姿勢や所作、相手への礼儀、ルールの遵守といった態度が評価対象になります。
加えて、局面ごとの押し引き判断や安全牌の扱いなど戦術的な部分もチェックされることが多く、総合力が試されるのです。
合格率は団体・期によって公表状況や数値が異なり、固定的な“平均値”は公式には示されていません。仮に合格したとしても、合格後に内部リーグで結果を残さなければ正式なプロ認定は得られません。
そのため短期間の準備ではなく、合格後を見据えた長期的な努力や計画性が不可欠といえるでしょう。
勉強方法と合格後の活動開始まで
合格に向けた勉強法としては、団体公式サイトの過去問やプロ解説動画を活用するのがおすすめです。これらは出題傾向を把握するだけでなく、現役プロの考え方や対局時の意識を学べる貴重な教材になります。
またネット麻雀や雀荘で経験を積みつつ、点数計算やルールを徹底的に学びましょう。特に点数計算は試験の基礎であり、スピーディーかつ正確に処理できる力が合格への鍵となります。
さらに、普段から礼儀や所作を意識して対局することで、実技試験での評価も高まりやすくなります。
✍合格に向けた流れ
- 公式サイトの過去問を解いて出題傾向を把握する。
- プロ解説動画を視聴して現役プロの思考を学ぶ。
- ネット麻雀や雀荘で実戦経験を積み、打ち筋を安定させる。
- 点数計算を徹底的に練習し、正確さとスピードを高める。
- 日常の対局で礼儀や所作を意識して身につける。
- 合格後は研修やリーグ戦に参加し、経験を積んで活躍の場を広げる。
このようなステップを踏むことで、合格だけでなくプロとしての活動開始後もスムーズに適応できます。合格後は各団体のリーグ戦や研修を経て、公式戦やメディア活動に参加できるようになり、ここで得られる経験はプロとしての財産となります。
加えて、自ら積極的に発信や勉強会に参加する姿勢も大切で、そこで活躍できるかどうかが、プロとしてのキャリアを左右していくのです。
麻雀プロになるには団体選びが重要

麻雀プロを目指すうえで、どの団体に所属するかは重要な決断です。団体ごとに理念や試験方法、活動方針が異なるため、自分の目標に合わない団体を選ぶと成長の機会を逃す恐れがあります。
メディア戦略や地方展開、育成制度も違うので、特色を調べ先輩プロの声を参考にしながら慎重に判断する必要があります。誤った選択は活躍の場を狭めるため、長期的視点で選ぶことが大切です。
主要団体(連盟・最高位戦・協会)の特徴
日本プロ麻雀連盟は国内最大規模で、Mリーグ選手も多数所属し、国内外の大会にも積極的に参加しています。試験は厳しいですが、合格すれば知名度や活動の幅が広く、解説やイベント出演の機会も豊富なのが魅力です。
最高位戦は伝統ある団体で、年齢制限がなく地方支部も活発に活動し、地方在住者でもプロ活動を続けやすい環境が整っています。
また、日本プロ麻雀協会は比較的新しい団体で、若手の育成や斬新な取り組みに積極的で、メディアやエンタメとの親和性が高いのも特徴です。
さらにYouTube配信やVTuberとのコラボなどにも取り組み、麻雀界の新しい風を生み出しています。
RMU・麻将連合の特色と地方対応
RMUは代表の多井隆晴プロの方針で、ファン目線を大切にした運営が特徴です。受験料が安く門戸も広い一方で、内部リーグを勝ち上がらなければ正式プロになれない仕組みを採用しています。
さらに育成システムや勉強会も整備されており、実力を段階的に磨ける環境があるのも特徴です。
麻将連合は競技性を徹底的に重視し、会員制度を経て段階的にプロ資格を得る厳格なスタイルを取っています。筆記や小論文など学術的要素も多く含まれ、合格後もツアー戦績によって認定を受けるため、純粋に競技麻雀を極めたい人に適しています。
地方対応では、連盟や最高位戦が全国に支部を持ち、北海道から九州まで幅広くカバーしており、地方からでも活動を始めやすい環境です。
これにより首都圏に住んでいなくても挑戦可能で、地方在住者にとってもチャンスが広がっています。
団体選びで意識したいポイント
団体選びでは、自分が競技性を重視したいのか、エンタメ性を重視したいのかを考えることが大切です。
たとえば本格的にタイトル獲得を目指すなら最高位戦や麻将連合が向いており、メディア出演や多方面での活動を望むなら連盟や協会が候補となります。
地方在住なら支部の有無も重要な要素で、全国展開している団体なら遠方からでも挑戦しやすいです。またSNSや動画配信を活用したい場合、メディア対応に積極的な協会やRMUが適しているでしょう。
さらに団体の雰囲気や先輩プロとの相性も長く活動するうえで大切な判断材料です。最終的には「この団体でやり抜きたい」と強く思えるかどうかが決め手となり、その覚悟が合格後の活動の原動力になるのです。
麻雀プロになるには知っておくべき活動と現実

麻雀プロの活動は多岐にわたり、公式戦や解説、配信活動まで幅広いのが実情です。さらに雑誌執筆やイベント出演、麻雀教室での指導といった活動もあり、活躍の場は年々多様化しています。
しかし収入面では厳しい現実もあり、華やかさの裏には地道な努力と継続が欠かせません。
そこで活動の幅や将来像を十分に理解し、自分のライフスタイルや目標と照らし合わせて挑戦することが大切です。
活動内容と収入源(リーグ戦・配信・Mリーグなど)
麻雀プロの中心は団体のリーグ戦やタイトル戦ですが、それだけでは収入は十分ではありません。多くのプロは雀荘勤務やイベント出演、解説業、YouTube配信など複数の収入源を組み合わせ、時には麻雀教室の講師や書籍の執筆といった仕事もこなしています。
イベントではファンとの交流を通じて人気を高め、解説業では安定した依頼を得ることで収入の柱にしている人もいます。
また、YouTubeやSNSでの発信は広告収益につながるだけでなく、スポンサー契約や企業案件の獲得にも直結する重要な活動です。
特にMリーグに所属すれば最低年俸400万円が保証され、知名度や安定した収入が得られるのが大きな魅力であり、ここを目指すことが多くのプロにとって最終的な目標の一つとなっています。
麻雀プロを目指し、活動していく場合は、麻雀プロの平均年収や収入の方法等を把握しておくことも重要なので、「麻雀プロの平均年収・収入」や「Mリーガーの平均年収・収入・推定年収ランキング」等にまとめた記事をぜひ併せてご覧ください!
メリットとデメリット、求められる発信力
麻雀プロになるメリットは、公式戦への参加資格や知名度向上、麻雀を仕事にできるやりがいです。さらにトッププロになればメディア露出が増え、書籍出版やイベント出演など活躍の場も広がります。
一方で収入は不安定で競争も激しく、多くの新人は副業を続けながら活動しています。
最近では実力に加えて、SNSやYouTubeを通じた発信力やファンサービスが重要視され、ファンを獲得できるかどうかが活躍の鍵となっています。
これらを総合的に考えると、麻雀プロは夢と厳しさが表裏一体の職業だといえます。
有名プロの事例と非プロでも活躍できる道
実際にMリーグで活躍する魚谷侑未プロや多井隆晴プロは、競技での実力と発信力を兼ね備えた代表例です。両者はリーグ戦での安定した成績に加え、解説やSNSでの積極的な情報発信によって幅広い層のファンを獲得し、麻雀界全体の認知度向上にも大きく貢献しています。
また、非プロでも、ネット麻雀の強豪や麻雀系YouTuberとして名を上げ、イベント出演等を果たすケースも少なくありません。
さらに最近ではVTuberや配信者が麻雀番組に出演し、その人気を足がかりに公式戦に招待される例も出てきています。
つまり麻雀の世界で活躍する道は一つではなく、競技・配信・指導など自分の得意分野を活かす工夫と、継続的に発信してファンを増やす努力が必要なのです。
麻雀プロになるには?の疑問によくある質問(Q&A)
Q. 麻雀プロ試験は誰でも受けられますか?
A. 基本的に18歳以上であれば受験可能ですが、高校生は不可の場合が多いです。団体によって年齢上限や条件が異なります。
Q. 合格率はどのくらいですか?
A. 大手団体では20〜30%程度と狭き門ですが、RMUや麻将連合では50%近い合格率とされます。ただし合格後も実績を残す必要があります。
Q. プロの収入は安定していますか?
A. 多くは雀荘勤務やイベント収入と組み合わせて生活しており、安定しているとは言えません。Mリーグ加入は安定収入の大きな道です。
Q. プロにならなくても活躍できますか?
A. はい、ネット麻雀や配信活動、YouTubeなどを通じて知名度を得て活躍する人も増えています。
Q. どの団体を選べばよいですか?
A. 自分が競技性重視かエンタメ重視かを考えて選ぶことが大切です。地方支部の有無や先輩プロの声も参考になります。
Q. プロ試験の勉強は何をすればいいですか?
A. 公式サイトの過去問やプロ解説動画を活用し、点数計算やマナーを徹底的に学ぶことが合格の近道です。
Q. Mリーグに入るにはどうすればいいですか?
A. 各団体で実績を積み、知名度や発信力を高めてドラフト指名を受ける必要があります。実力と人気の両立が重要です。
Q. 女性でも麻雀プロになれますか?
A. もちろん可能です。女流プロ制度や女性限定のツアー制度がある団体もあり、女性プレイヤーは年々増えています。
Q. プロとしての活動費用はどれくらいかかりますか?
A. 年会費やリーグ参加費で年間数万円程度が必要で、遠征費や研修費も含めると負担は少なくありません。
Q. プロ資格を取得すればすぐに仕事は得られますか?
A. 団体に所属するだけでは仕事は自動的に与えられません。自ら発信し、ファンを獲得することで仕事の幅が広がります。
Q. 非プロからMリーグ入りは可能ですか?
A. いいえ、Mリーグのドラフト対象は5団体に所属する“プロ雀士”に限定されています。アマや配信者として実績と発信力を高め、プロ団体に所属した上でドラフト候補になるのが実際的な道です。
Q. 麻雀プロの資格だけを取った後に活動しなくても問題ないですか?
A. 団体に所属し続けていれば形式上は問題ありませんが、活動実績がなければ信頼や評価は得られません。長期間活動しないと在籍を続ける意味が薄れ、会費の負担だけが残ることになります。結果的にプロとしての価値は低下してしまうため、できる限り大会やイベントに参加することが望ましいです。
詳しくは「 麻雀プロの資格だけを取った後に活動しなくても問題ないか」について整理した記事をご覧ください!

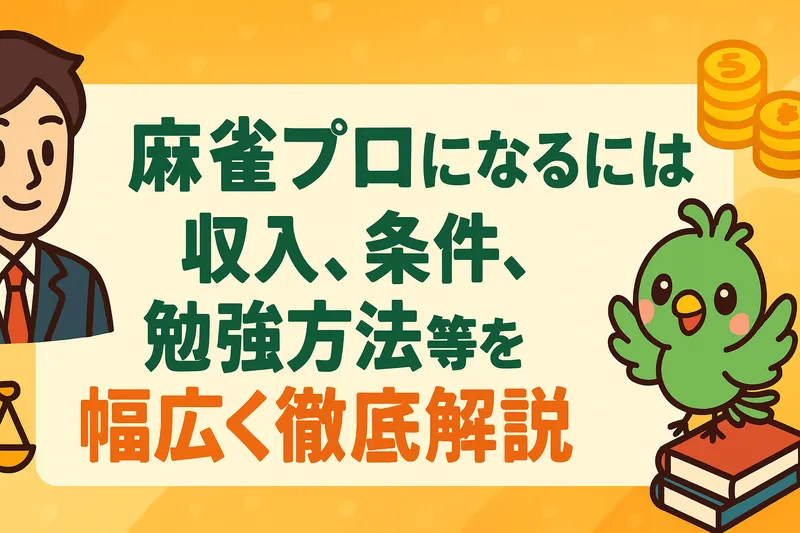
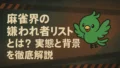

コメント