「リャンメン待ちって強いらしいけど、実際どれほど差が出るの?」
そんな疑問を抱えている方に向けて、本稿では麻雀における両面(リャンメン)待ちを完全解説!和了率と押し引きの最適解の基本的な仕組みから、なぜ受け入れ枚数が多く和了率が高いのかという牌効率の理論、さらに具体的な待ちの比較やリャンメン化するためのターツ選択方法まで徹底解説します。
また、押し引きの基準や守備面での注意点を巡目観点で網羅的に説明。天鳳8段の実戦経験を踏まえつつ、読者の皆さんが次の対局からすぐに活用できるように詳しくガイドします。
これを読めば、リャンメン待ちを軸とした手作りの精度が劇的にアップすること間違いなしです!こういった牌の形は、麻雀の初心者が勝ち方やコツを身に着けていく上で重要な要素なので、ぜひ最後までご覧ください!
麻雀の両面(リャンメン)待ちを使いこなす基本と牌効率

リャンメン待ちの成立条件と具体例
リャンメン待ちは、麻雀における最も基本的で効率的な待ちの形です。順子(シュンツ)を完成させるために、連続する2枚の数牌(例えば
 )を持ち、その両端の牌(この例では
)を持ち、その両端の牌(この例では と
と )を待つ形を指します。この形では、待ち牌が2種類あり、それぞれ4枚ずつ存在するため、最大で8枚の受け入れ牌が存在します。
)を待つ形を指します。この形では、待ち牌が2種類あり、それぞれ4枚ずつ存在するため、最大で8枚の受け入れ牌が存在します。
以下に、リャンメン待ちの具体例を示します。
- 例1: 手牌に

 を持っている場合、
を持っている場合、 または
または を引けば
を引けば

 または
または

 の順子が完成します。
の順子が完成します。 - 例2: 手牌に

 を持っている場合、
を持っている場合、 または
または を引けば
を引けば

 または
または

 の順子が完成します。
の順子が完成します。
これらの例のように、リャンメン待ちは順子の両端を待つ形であり、和了牌が2種類存在するため、非常に効率的な待ちとされています。
さらに、リャンメン待ちは他の待ち形と比較してもその優位性が際立っています。例えば、カンチャン待ちやペンチャン待ちは待ち牌が1種類で最大4枚、シャンポン待ちは2種類で最大4枚と、リャンメン待ちの8枚に比べて受け入れ枚数が少なくなります。
そのため、リャンメン待ちは和了の可能性が高く、基本的な待ち形として重視されています。
このように、リャンメン待ちは麻雀において最も基本的でありながら、非常に効率的な待ちの形です。初心者から上級者まで、リャンメン待ちを意識した手作りを心がけることで、和了率の向上が期待できます。
受け入れ最大8枚が生む速度と和了率の優位性
受け入れが多ければ牌効率が良くなり、和了巡目も早いです。
9巡目リャンメンリーチ→最後までツモった際のツモ率は50%程度とされ、同巡目カンチャンでは30%程度以下に落ちます。つまり、和了できるかどうかの勝負所で、リャンメンを選べるかどうかが大きな分かれ目になります。
手牌の速度が遅ければ、他家が聴牌勝負に負けるため、放銃率・被ツモ率にも影響します。つまり、トップを狙ううえで「良形追求」は外せませんし、安定して勝ち続けるための基本姿勢として、常にリャンメン化を意識した手組みを優先すべきでしょう。
カンチャン・ペンチャン・シャンポンとの受け入れ比較
複数ある待ち形の中で、リャンメンがなぜ特別なのか――その強さを際立たせるには、他の待ちと比較してみるのが一番です。
ここでは、代表的な4つの待ち形について、それぞれの受け入れ枚数や特徴を簡潔にまとめてみました。
- リャンメン待ち
- 🀄 受け入れ:8枚(最大)
- 💡 特徴:和了速度・効率ともに最強レベル。
- カンチャン待ち
- 🀄 受け入れ:4枚:4枚
- 💡 特徴:一手変化でリャンメンになるため、手組みに余地あり。
- シャンポン待ち
- 🀄 受け入れ:4枚(2種×2枚)
- 💡 特徴:序盤攻めやスジ読みを活かした待ちとして有効。シャンポン待ちも一手変化でリャンメンになる
- ペンチャン待ち
- 🀄 受け入れ:4枚
- 💡 特徴:端牌絡みで手広さはやや劣る。打点も控えめになりがち。一手変化でリャンメンにはならない
数字だけ見れば、リャンメンはカンチャン待ち・シャンポン待ち・ペンチャン待ちよりも安定感はやはり圧倒的な形です。 迷ったときこそ、8枚の受け入れを信じて勝ちをつかみましょう!
両面(リャンメン)待ちへ導く切り順とターツ選びで麻雀を速攻

端牌整理とターツ優先度でリャンメン化するセオリー
基本は「19字牌→ペンチャン→対子→カンチャン」の順で処理するのが牌効率的に良いです。端牌1・9はリャンメン素材にならないため、序盤に切るだけでターツ総数が+1枚増えることも。中張牌(2〜8)を中心に手牌を構成することで、将来的なリャンメン変化のチャンスも広がります。
また、ターツがあふれた際の判断も重要です。カンチャンやペンチャンが残っていたら、変化の幅や打点の伸びしろを考慮しつつ、最も受け入れの多いリャンメンを優先して残しましょう。受け入れが同程度なら、赤ドラや役絡みの可能性が高いターツを残すのも一つの選択肢です。
ターツ選びの判断基準を明確にしておくことで、テンパイまでの速度が安定し、リーチや平和などの役構成にもつなげやすくなります。
良形6枚以上なら即リー!
現代系シミュレーションの代表例として、「麻雀数理研究室」様が公開した約470万局の牌譜解析では、先制リーチかつ良形6枚以上の平均局収支は+1100〜+1400点、ダマ選択との差はおおむね+800点以上と報告されています。
また『「統計学」のマージャン戦術 』に掲載された別統計でも、同条件の和了率は49〜53%、放銃率は23〜26%に収束しており、押し返されてもトータルで黒字を維持できると示されました。
良形を掴んだら積極的に曲げる――これが収支を安定させる近道というのが複数データに共通する結論です。
リャンメン待ちで攻めるか降りるか?押し引き基準
リャンメン待ちはアガリ率が高く、基本的にはリーチが有利ですが、状況により慎重な判断も必要です。以下に押し引き基準を整理しました。
- 先制リャンメンテンパイは基本的にリーチ
- アガリ率の高さ:先制リャンメンリーチのアガリ率は約50〜60%と高く、特に端牌待ち(

 や
や
 など)はアガリ率がさらに上昇します。
など)はアガリ率がさらに上昇します。 - 打点の期待:リーチによる打点上昇や裏ドラの期待もあり、平均収支が高くなる傾向があります。
- アガリ率の高さ:先制リャンメンリーチのアガリ率は約50〜60%と高く、特に端牌待ち(
- 中盤以降の押し引き判断
- 巡目と待ち牌の見え方:中盤以降、待ち牌が場に多く見えている場合はアガリ率が低下します。押すか引くかの判断基準として重要です。
- 相手のリーチ状況:相手からリーチが入っている場合、自分の手牌の打点や安全牌の有無を考慮して判断します。
- 終盤の押し引き基準
- 安全牌の確保:終盤で安全牌がない場合、無理に押すと放銃リスクが高まります。安全牌があれば降りを検討。
- 点数状況の考慮:自身の点数状況や親・子の立場でも判断は変化します。親であれば積極的に押すケースもあります。
リャンメン待ちは強力ですが、局面ごとの状況を把握して最適な判断を下すことが大切です。
天鳳8段になれた押し引き基準・表をまとめたので、ぜひ読んでください!
また、押し引きが上手くなる名著は下記ですので、ぜひ購入して読んでみてください!Amazonだと安く購入できるため、おすすめです!
【総括】麻雀の両面(リャンメン)待ちのまとめ
▼この記事のポイントまとめ



 を持っている場合、
を持っている場合、 を引けば
を引けば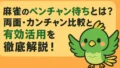

コメント